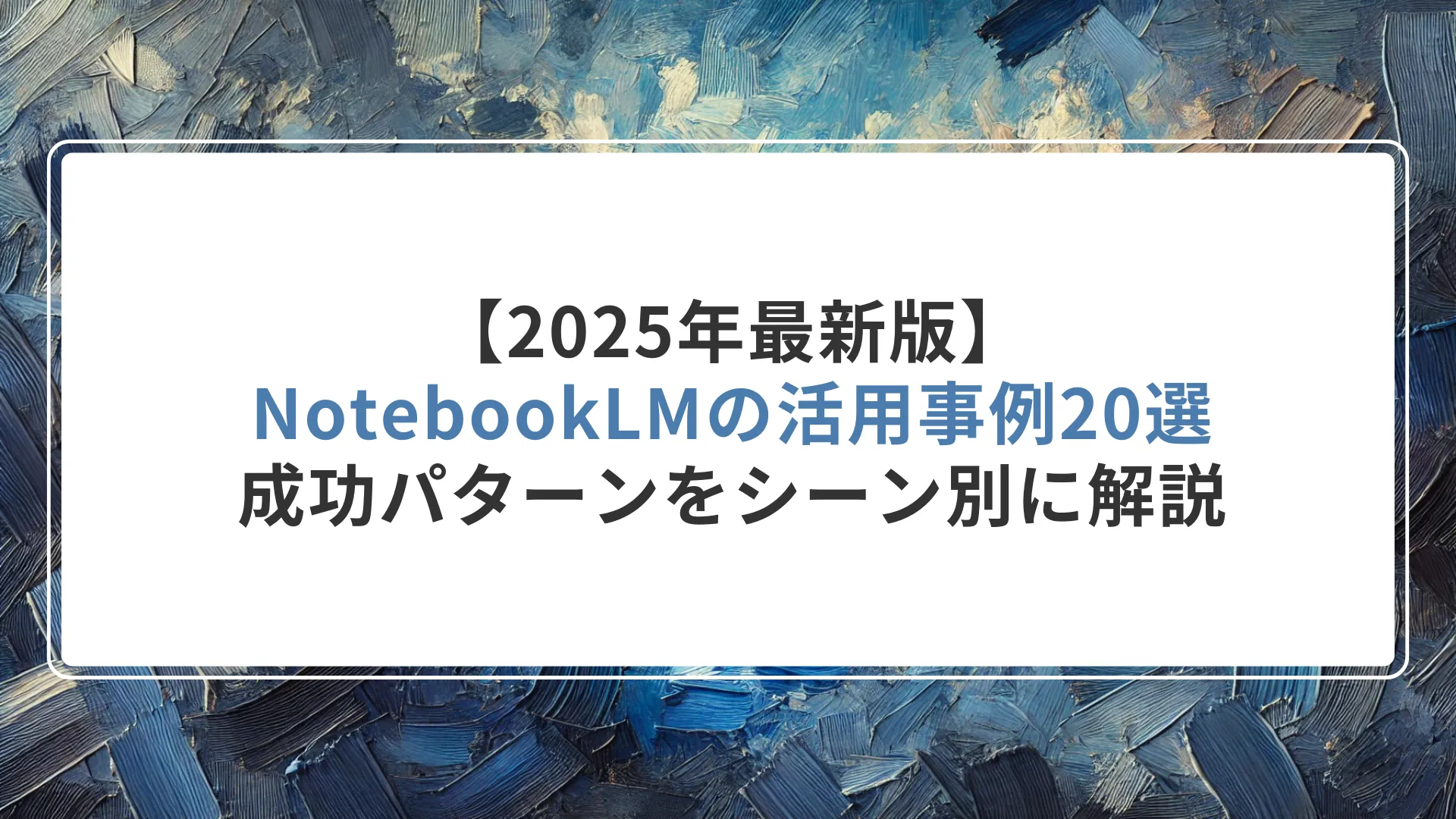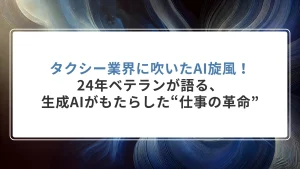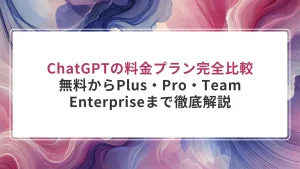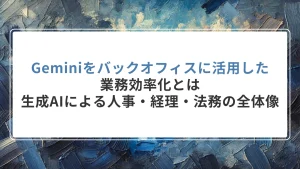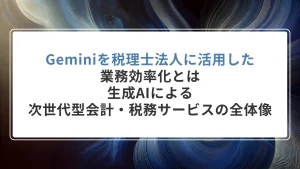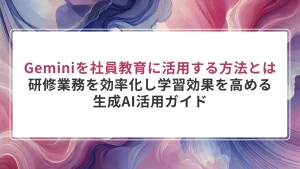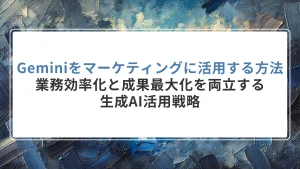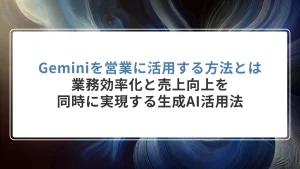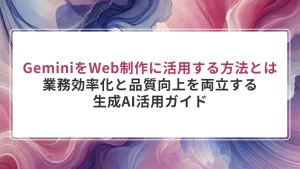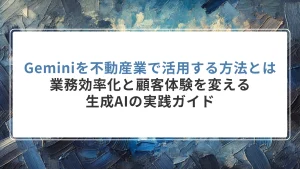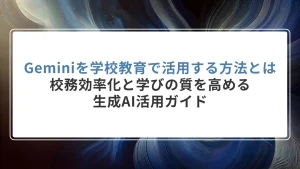「情報をどうまとめるか」は、ビジネスでも学習でも研究でも、成果を左右する大きな鍵です。
Googleが開発したNotebookLM(ノートブックエルエム)は、その鍵を“AIの力”で解決するために生まれたツールです。
NotebookLMとは、自分がアップロードした資料やURLなどをもとに、AIが要約・質問応答・構造化整理をしてくれるパーソナルナレッジアシスタントです。
単なるAIチャットボットではなく、「自分専用のAIリサーチャー」や「資料整理ロボット」のような立ち位置で使えるのが特徴です。
知識労働の現場では、情報の整理と再活用こそが生産性を高める鍵になります。NotebookLMはまさに、個人にも企業にもフィットする”ナレッジ整理の特化型AI“として急速に注目されています。
そんなNotebookLMの活用事例をこの記事では紹介しています。
NotebookLMとは何か知らない方は、先にこちらの記事をご覧ください。
NotebookLMの主な機能

要約・要点抽出
複数のPDF、Word、テキスト、Webページなどをアップロードすると、AIが内容を横断的に読み込み、重要ポイントを要約。
「この資料の主張は何?」「重要な数字はどこ?」といった質問にも瞬時に対応します。
質問応答(Q&A)
アップロードした資料の内容に基づいて、自然な対話で質問ができます。回答には出典リンクが自動で付くため、情報の裏取りや再確認も容易です。
マインドマップ化
要約した情報をビジュアルで俯瞰できる「マインドマップ」機能。議論の構造や関係性を把握しやすくなり、情報整理・発想支援に効果的です。
音声・動画要約(Audio/Video Overview)
AIが資料の要点をナレーション音声や簡易スライドに変換。通勤中や作業中でも“耳から学べる”ため、ながら学習にも便利です。
ノートブックの共有・公開
作成したノートは個人用として保存するだけでなく、リンク共有で社内や外部とも簡単に情報共有可能。
さらに、NotebookLM Studioを使えば、ノートをプレゼン資料として自動変換することも可能です。
NotebookLMの主な活用シーンとは?
NotebookLMの魅力は、単なるAIツールではなく、“現場に応じた柔軟な使い方”ができることです。
そしてそれは、業種や目的によってその表情を大きく変えます。
ここでは、実際の利用者がどうNotebookLMを活用しているかを踏まえながら、代表的なシーンを整理してみましょう。
ビジネス現場での活用
- 会議議事録の要約・アクション抽出:
会議資料や録音データをアップロードすることで、NotebookLMが要点やタスクを明示。決定事項の見落とし防止や、次回会議への引き継ぎがスムーズに。 - 営業・企画提案の構成支援:
過去の提案書や競合情報、ヒアリング記録を整理し、「この案件に最適な提案は?」と質問すれば、説得力あるたたき台を即生成。 - 社内FAQ/ナレッジベース構築:
社内マニュアルやルール文書をまとめて読み込ませれば、社員からの質問に即座に根拠付きで回答可能。自己解決率が飛躍的に向上します。
教育・学習における活用
- 資格試験対策・予習復習:
教材や過去問をアップして「第2章の出題ポイントは?」などと尋ねれば、重要ポイントをQ&A形式で確認可能。模擬試験の“壁打ち相手”にもなります。 - 研修資料・講義ノートの要約:
長大な研修資料や講義スライドをNotebookLMに読み込ませ、要点をまとめ直したり、理解度チェックのクイズを自動生成できます。 - 音声要約での“ながら学習”:
通勤や家事中に、NotebookLMが資料の概要を読み上げ。テキストでの学習が難しいシーンでも知識を吸収できます。
研究・開発での活用
- 論文レビューと比較整理:
NotebookLMに複数の論文や特許を読み込ませ、「AとBの手法の違いは?」「主要な技術要素は?」と質問することで、煩雑な文献レビューが劇的に効率化されます。 - 文献管理とナレッジ蓄積:
分野ごとに参考文献を分類管理し、「○○について述べている文献は?」といった情報探索もスムーズになります。 - 研究プロジェクトの進捗・議論管理:
プロジェクト関連資料を一括で管理し、議事録や進捗レポートから「どんな課題が上がっていたか?」などの分析にも活用できます。
クリエイティブ・ライティング分野での活用
- 記事構成・下書き支援:
取材メモや関連資料をNotebookLMにアップして「この記事の構成を考えて」と頼めば、テーマに沿った骨子や導入文案が提示され、ライター業務が高速化されます。 - 情報収集とネタ出し:
複数の業界資料をもとに「どんなトピックが注目されている?」と尋ねることで、SEOに強いコンテンツ案やSNS投稿のネタ出しがスムーズになります。 - 英語コンテンツの翻訳・理解:
英語論文や海外文献をアップしてNotebookLMで日本語要約させることで、言語の壁を越えて情報収集と理解が可能になります。
【活用事例20選】シーン別に見るNotebookLMの活用事例と成功パターン
ここからは、実際のユースケースやユーザー事例をベースに、NotebookLMの代表的な活用方法を20例ピックアップして紹介します。
検索ユーザーが最も知りたい「自分に合った使い方」のヒントがきっと見つかるはずです。
ビジネス活用編
- 会議議事録の自動要約とアクション抽出
会議資料・音声をアップし、「決定事項は?」「次回までのタスクは?」と質問。漏れなく整理。 - 営業トークスクリプトの自動生成
過去の提案書・パンフレットを読み込ませ、新人営業でも使える“トークのたたき台”を生成。 - プロジェクト進捗の一元管理
議事録やタスク表をノートブックに集約。「今どこまで進んでる?」「問題点は?」と確認可能。 - 社内ナレッジベースの構築
社内マニュアルをアップし、「○○の手続きって?」「経費申請の注意点は?」に即回答。 - 社内FAQチャットボット化
NotebookLMに質問すれば、根拠付きで答えを出力。人事・総務系の問い合わせ削減に◎。
マーケティング活用編
- SEO記事の構成・企画支援
業界資料を読み込ませて、「このトピックでよく出てくるワードは?」「未カバーのテーマは?」を抽出。 - SNS投稿のパフォーマンス分析
過去の投稿内容と反応データを読み込み、「反響が大きかった投稿に共通する要素は?」と分析。 - 顧客レビューやアンケートの傾向把握
NotebookLMが満足点・不満点を分類整理。「改善要望TOP3は?」という質問に一発回答。 - 競合他社の開示情報の要点抽出
ホワイトペーパーやIR資料を読み込ませて、「A社とB社の戦略の違いは?」と比較分析。 - マーケティング施策のアイデア出し
過去の実績資料と業界レポートを統合し、成功要因から新施策を導くブレインストーミング支援。
教育・学習活用編
- 資格試験の壁打ち練習
教材PDFを読み込ませ、想定問答を繰り返して「この項目、ちゃんと理解できてる?」をチェック。 - 教材要約とクイズ生成
研修スライドをアップして「要点を3つにまとめて」「内容確認クイズを作って」と頼めば即出力。 - 音声学習によるインプット効率化
通勤時間にAudio Overviewで“聞きながら学習”。読めない時も知識を吸収できる。 - 勉強会の事前資料整理
複数人の発表資料を1冊のノートにまとめて、全体の要点をNotebookLMにまとめてもらう。 - 学生のレポート作成補助
課題資料や文献をまとめ、「このテーマの背景は?」「主張の根拠は?」と探るQ&A学習に最適。
研究・開発活用編
- 複数論文の比較要約
医学・技術論文をまとめて読み込ませ、「主張の違いは?」「どっちが新しい手法?」などを整理。 - 参考文献管理と引用整理
「○○について触れてる文献は?」と聞けば、該当文献+該当箇所をピンポイントで教えてくれる。 - プロジェクト資料のナレッジ化
社内ドキュメントを時系列で整理し、「この技術の検討履歴は?」「どんな議論があった?」も明確に。
クリエイティブ活用編
- 記事や企画書の構成支援
NotebookLMにインプットを渡し、「この資料からWeb記事の構成を考えて」と依頼すれば、論点整理・導入文案まで自動化。 - 翻訳された資料の理解促進
英語資料+NotebookLM+翻訳ツールの組み合わせで、専門的な海外情報も日本語でしっかり咀嚼可能。
NotebookLMを使いこなす5つのコツ
NotebookLMはシンプルに見えて、ちょっとした工夫で使い勝手と精度が飛躍的に向上するツールです。
ここでは、実際のユーザーや専門家が実践している、効果的な使い方の「5つのコツ」を紹介します。
1. ノートブックは目的別に分けて使う
NotebookLMでは1つのノートブックに最大50件まで資料をアップロードできます。
しかし、異なるテーマの資料を1冊に詰め込むとAIの文脈理解が鈍ることも。営業資料、契約書、論文、研修資料などは用途ごとにノートブックを分けるのが鉄則です。
例:「顧客対応ノート」「資格勉強ノート」「競合調査ノート」など、名前を付けて整理すると管理もラクになります。
2. 質問は具体的かつ一つずつ段階的に
NotebookLMは「文脈を持った対話AI」ではなく、「1問1答型のナレッジ抽出ツール」に近い性質があります。
そのため、複数の質問を一度に投げたり、抽象的な問いかけをすると精度が下がる傾向があります。
✔ 「このレポートの主張は何?」→「その根拠は?」→「関連する事例は?」というように、一つずつ段階的に尋ねるのがベストです。
3. 出典リンクで必ず答えの裏付けを取る
NotebookLMの優れた点は、回答に必ず元データの“引用リンク”が付くことです。
これは他のAIツールにはあまり見られない強みであり、ビジネスや研究の現場での活用には特に重要です。
✔ 「この数値って本当に資料に書いてあるの?」と不安な時は、出典リンクをクリックして即確認できます。
4. Audio Overviewを活用して“耳から”学ぶ
忙しくて資料を読む時間がない人こそ、音声要約機能(Audio Overview)を使うべきです。
NotebookLMは、AIが要点をナレーション形式で読み上げてくれるため、通勤中・作業中でも学習が可能になります。
✔ 英語音声に加え、日本語対応も進行中。スキマ時間を最大活用する“ながらインプット”に最適です。
5. 機密情報の取り扱いは慎重に
NotebookLMはプライバシー設計に配慮されており、ユーザーデータをAI学習に利用しないとされています。
とはいえ、企業の内部資料や契約書などのアップロードには慎重さが求められます。
✔ 対策例:重要情報はマスキング/匿名化して使用、概要のみアップして本体データは別管理、社内ルールの確認 etc.
今後のNotebookLMに期待される進化
NotebookLMは、まだ進化の途上にあるツールです。
Google自身が「生成AIによる知識整理の未来を切り開く」と位置付けており、今後も次々と新機能が追加される見込みです。ここでは、注目されている進化ポイントを紹介します。
1. Audio & Video Overviewの正式展開
現在ベータ機能として提供されている「Audio Overview(音声要約)」に加え、資料から“動画スライド形式”の要約を自動生成する機能が導入され始めています。
これは、要点を箇条書き+ナレーション付きスライドで表示し、視覚と聴覚を両方使って情報を理解できる仕組み。
プレゼン準備、eラーニング、動画マニュアルの生成などに応用が期待されています。
2. ノートブックの共有・公開機能の拡張
従来は個人利用や社内共有にとどまっていたNotebookLMですが、「パブリック共有(リンク共有)」機能が強化され、Webでの情報発信にも活用できるようになりました。
- 勉強会のノートを参加者に共有
- 企業のホワイトペーパーをNotebookLM化して外部公開
- 公開Q&AノートでSEO集客につなげる
など、**ナレッジの“公開資産化”**が進んでいくと予想されます。
3. 他ツールとの連携(API/Google Workspace)
API連携の開放が予告されており、近い将来、以下のような連携も可能になると見られています:
- Google DocsやDriveとの自動同期
- Gmail内の資料を自動インポートして要約
- 外部サービス(Notion、Slack、Teamsなど)との連携でワークフロー自動化
これにより、NotebookLMは「AIが常駐する知識インフラ」として、日常業務に完全に溶け込む存在になるでしょう。
4. エンタープライズ利用への対応強化
今後、企業向けに特化した有料プランやセキュリティ強化オプションが拡充される可能性も指摘されています。
特に、アクセス制御やログ管理、SAML認証など、エンタープライズレベルのガバナンス要件に応える仕様が求められています。
まとめ:NotebookLMは知的生産の“加速装置”になる
NotebookLMは、情報過多の時代における「ナレッジの整理整頓役」として、多くの知的労働者にとって頼れる存在になりつつあります。
膨大な資料を読み込んで要約し、質問に答え、図に整理し、音声や動画に変換する――これらを**“数分で”こなすAIパートナー**は、従来のツールとは一線を画します。
本記事では、ビジネス、マーケティング、教育、研究、クリエイティブの各分野における活用事例を紹介しましたが、共通して言えるのは以下の3点です:
✅ NotebookLMが生む3つの価値
- 時間の節約:
情報収集・要約・整理にかかる時間を大幅に削減。 - 理解の深まり:
複数の資料を“構造的に”読み解くことで、本質が見えやすくなる。 - 知識の共有:
自分のノートをそのまま他者と共有できるため、チーム全体の知的生産性が上がる。
🎯 NotebookLMを始めるなら、まずこの使い方から!
- 初心者なら「会議議事録」や「読書ノート」の要約から始めてみましょう
- 学習者なら「資格対策」や「授業スライドの要点整理」に
- 企業担当者なら「社内FAQ構築」や「営業提案支援」に応用可能です
NotebookLMは「使うほど、仕事のやり方が変わる」ツールです。
あなたの情報活用スタイルに、AIという名の“加速装置”を組み込んでみませんか?