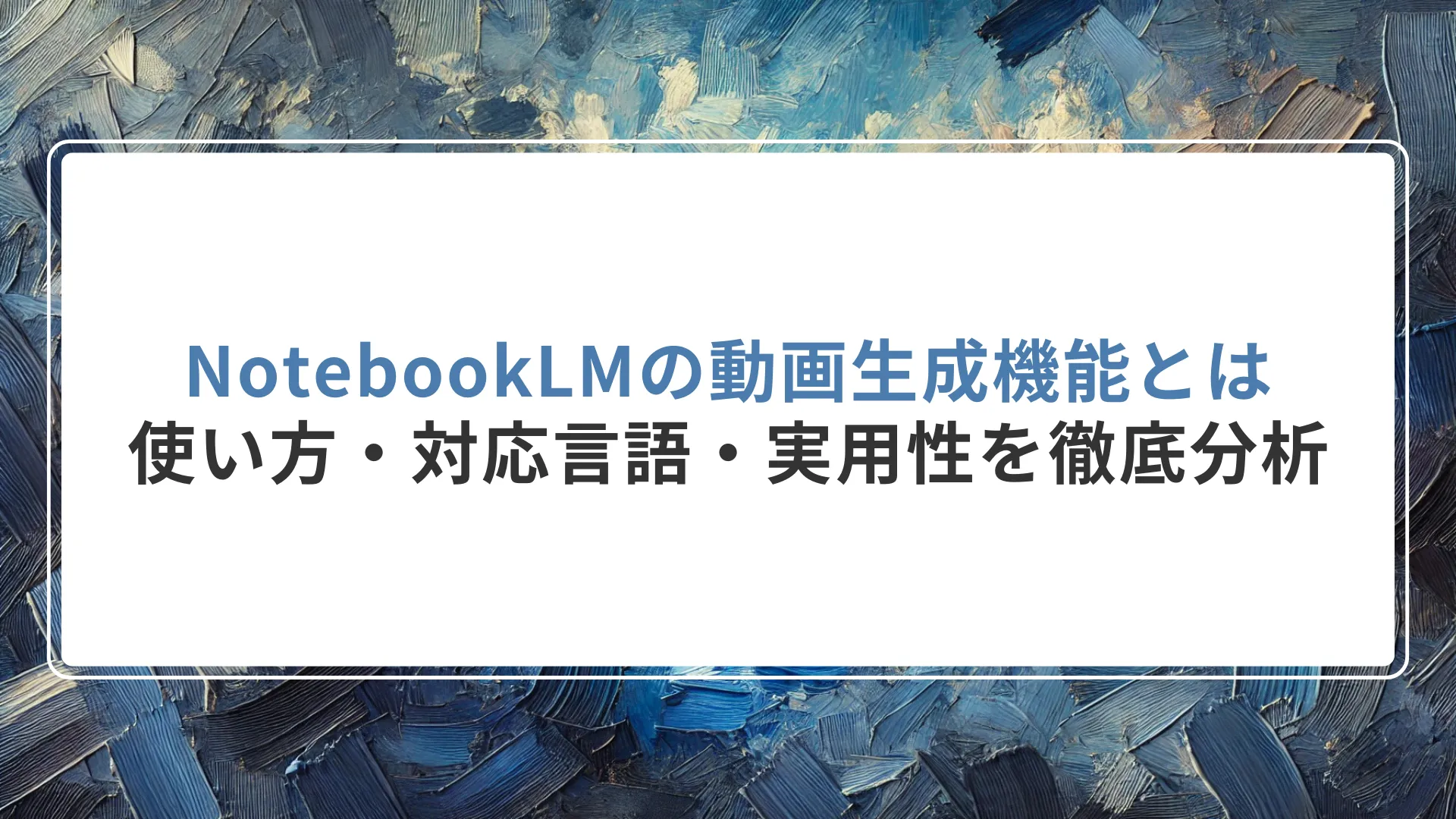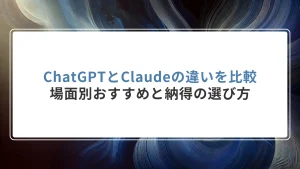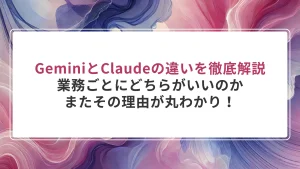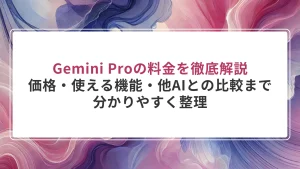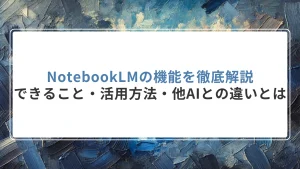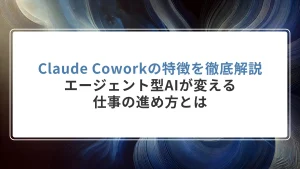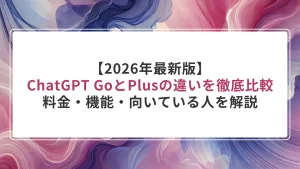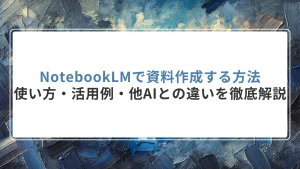テキストだけでは伝わりにくい情報を、視覚と音声で補完する「動画」という形式。その生成をAIに任せることができるとしたら──Google NotebookLMが提供する「動画解説(Video Overviews)」は、まさにそのニーズに応える機能です。従来のナレーション付きスライドショーとは一線を画し、ユーザーが信頼する情報源に基づいて、明確かつ戦略的に要約された動画を自動生成します。本記事では、検索ユーザーが最も気にしている「どんな動画が作れるのか」「何本作れるのか」という疑問に答えながら、実際の使い方やユースケース、技術的な制約も含めて解説します。
NotebookLMの動画生成機能(Video Overviews)とは?
Google NotebookLMの「動画解説」機能は、ユーザーが提供したソース(PDF、Googleドキュメント、YouTubeのURLなど)を基に、AIが自動で要点を抽出し、スライド形式の動画を作成するものです。特徴的なのは、スライドそれぞれにAIナレーsションが付き、視覚と聴覚の両面から情報を伝える点。これは単なる要約機能ではなく、NotebookLMが「思考のパートナー」として進化する象徴でもあります。
実際に生成される動画はどんな内容?
生成される動画は平均7分程度。スライドごとに図表・引用・画像などが整理され、落ち着いたAI音声が内容を読み上げます。音声とビジュアルは完全自動生成。画像が不足する場合は、AIが文脈に合ったビジュアルを新たに作り出します。
ただし、現時点ではプレゼンテーション形式に限定されており、動的なアニメーションや派手な演出は存在しません。また、一部ユーザーからは音声の途切れや、スライド遷移時の不自然さに関するフィードバックも寄せられています。
作成してみた動画はこのようなものです。
どれくらいの動画を生成できるのか?
現状、1つのNotebook内で複数の「動画解説」を生成・保存できます。NotebookLMのStudioパネルでは、テキスト要約、音声解説、マインドマップ、動画解説の各形式を並行して出力・保存可能。用途に応じて、異なる焦点を持つ動画を複数作成することも可能です。
また、生成プロセスはバックグラウンドで処理されるため、作業中に並行して他のアウトプットを作成できます。生成にかかる時間は、コンテンツの長さや内容により異なりますが、7分の動画で約10〜15分程度と見込まれています。
多言語対応とその意義
Googleは2025年8月にNotebookLMの多言語対応を大幅に強化し、現在では80以上の言語で「動画解説」を生成可能にしています。日本語はもちろん、ヒンディー語、タミル語、フランス語など、各国の主要言語を網羅。これは、教育機関やグローバル企業にとって、特に大きな価値をもたらします。
動画生成時には、ユーザーが任意の言語を指定可能で、学習者向け・専門家向けなど、ターゲットに応じた最適なコンテンツ出力が可能です。
利用する際の技術的注意点
- 生成時間:平均7分の動画で10〜15分程度の生成時間がかかることがある
- 音声の不安定さ:ナレーションとスライドの切り替え時に音声が途切れるケースあり
- 出力形式:MP4動画としてダウンロード可能。なお、Workspace EnterpriseやEducationアカウントでは、リンクでの外部公開に制限があります
これらの点を踏まえたうえで、業務フローや教材設計に組み込む必要があります。
利用シーンとユーザー層別の活用提案
- 学生・教育関係者:講義ノートや研究資料の要点整理に
- ビジネスパーソン:会議資料の事前共有や、プレゼンの下準備に
- AI導入を検討する企業:社内ドキュメントの効率的な伝達手段として
情報を「見える化」し、「伝わる形」に変換します。特に時間的コストを抑えたい現場において、非常に有効な手段となるでしょう。
今後の展望とGoogleの戦略
Googleは今後、「Magic View」と呼ばれる新たなビジュアライザーの導入を予定しており、よりインタラクティブで動的な出力への進化が示唆されています。これは、NotebookLMが単なるドキュメント整理ツールから、「知識と創造性を橋渡しするAIパートナー」へと脱皮していく過程の一部に過ぎません。
結論と戦略的提言
Google NotebookLMの「動画解説」機能は、単なる新機能ではなく、AIを用いた情報伝達の新しい形です。現在はスライドショー形式に限定されているとはいえ、その「情報の正確性」と「再利用性」は非常に高く、教育やビジネスの現場で即戦力として活用できます。
目的が「創造的な映像制作」ではなく、「わかりやすい要約と共有」であるならば、NotebookLMの動画生成機能は、まさにそのニーズに合致したソリューションです。