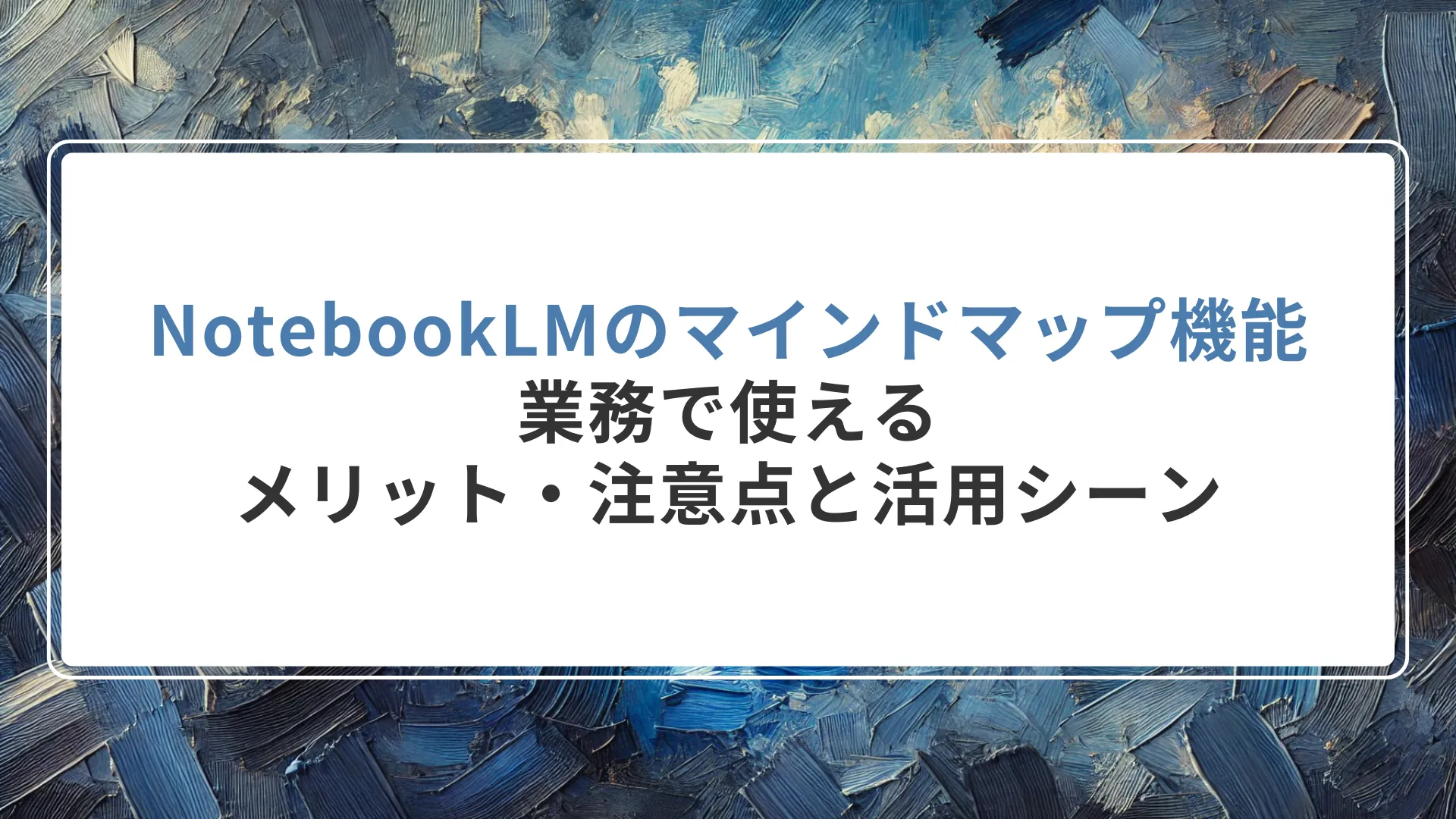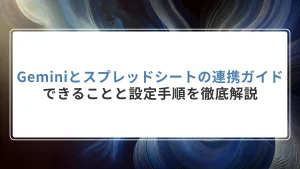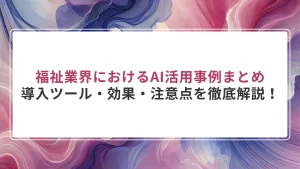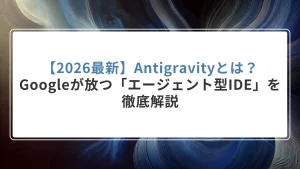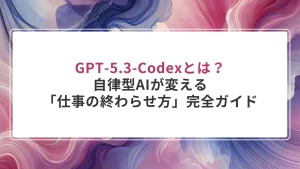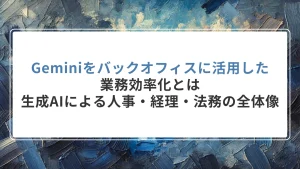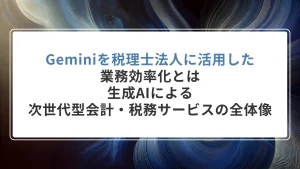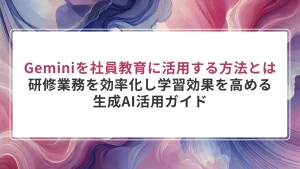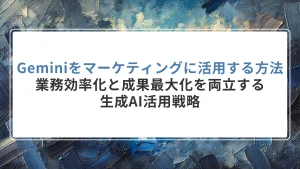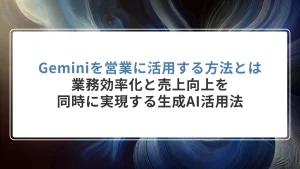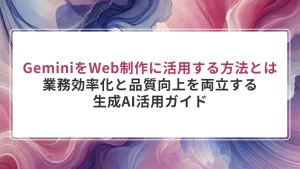ビジネスの現場では、資料・議事録・調査レポートなど膨大な情報を扱う機会が増えています。ところが、その全体像を短時間で掴み、次のアクションにつなげるのは容易ではありません。
こうした課題に応える存在として注目を集めているのが、Googleが提供するAIノートツール「NotebookLM」。その中でも「マインドマップ機能」は、情報をAIが解析し、直感的に理解できる構造に変換してくれる革新的な仕組みです。
NotebookLMのマインドマップ機能の概要
NotebookLMでは、PDF・Googleドキュメント・Webページ・動画の文字起こしなど多様な資料をアップロードできます。AIがこれらを解析し、主要なテーマを中心に据え、関連するサブトピックを放射状に展開するマインドマップを自動生成します。
特筆すべきは、生成されたマップが単なる静止画像ではなく「インタラクティブに操作できる点」です。ノードをクリックすれば枝を展開・折りたたみでき、気になる項目を選択するとその要約や解説がチャット欄に表示され、理解を深めながら探索を続けられます。
さらに、完成したマップはPNG形式で保存したり、ノート全体を共有できるため、チームでの共同作業にも適しています。
業務で使えるメリット
業務に直結する複数の強みがあります。
- 長文資料や複数資料の全体像を瞬時に把握できる
従来なら数時間かかる構造整理が、数分で完了します。 - 情報の関連性を可視化できる
バラバラの文書に含まれるテーマや概念のつながりを、一目で理解可能。 - チーム共有に最適
複雑な内容も視覚化することで誤解を減らし、議論をスムーズにします。 - アイデア発想を支援
放射状のマップは、新しい関連性や抜け漏れを発見する契機になります。
注意点・制約
一方で、導入にあたって知っておきたい制約も存在します。
- 自由編集ができない
ノード名や構造を細かく調整する機能はなく、AIが生成した形をそのまま活用する前提となります。 - AIの精度に依存
重要でない項目が抽出されたり、逆に必要な要素が欠ける可能性があります。 - セキュリティへの配慮が必要
機密性の高い文書を扱う場合には、社内ポリシーとの整合性を検討すべきです。 - 無料版と有料版で機能差がある
大量データや大規模運用には有料プランが前提となるケースがあります。
業務・分野別の活用シーン
以下のように幅広い領域で応用可能です。
- ビジネス現場
- 会議資料や議事録を解析し、議題・決定事項・担当者をマップ化
- プロジェクトのタスクや依存関係を整理し、全体像を共有
- 組織図や体制をマップ化して、新メンバーへの説明を効率化
- マーケティング/顧客分析
- 顧客アンケートやサポート履歴を取り込み、AIが「改善要望」「高評価ポイント」に分類
- 頻出する課題を視覚化し、改善施策を立案
- 研究・アカデミア
- 複数の論文をまとめて読み込み、研究テーマの主要概念や関連性を可視化
- 学会発表前に議論の全体像を整理
- 教育/学習
- 教科書や講義ノートをアップロードし、概念のつながりをマップ化
- 学習者が全体像をつかみやすく、理解度が向上
- 起業家・クリエイター
- ビジネスモデル設計やアイデア出しをマップ化し、抜け漏れをチェック
- ブログ記事やレポートのアウトラインをAIに生成させ、効率的に構成を作成
- 個人利用
- キャリアプランやライフイベントをマップ化し、自分の選択肢を整理
- 趣味や学習テーマを構造化して、新しい視点を得る
どんな人に向いているか
特に効果を発揮するのは、次のような状況です。
- 膨大な情報を扱い、全体像をすぐに掴む必要がある人
- 複数ドキュメントの関係性を整理し、チームで共有したい人
- アイデア発想や企画構築を効率化したい人
逆に、以下のような場合は他のツールを検討した方が良いかもしれません。
- 自分で細かくノードや構造を編集したい場合
- 単純な資料のみでマインドマップを使う必要がない場合
- 高度なセキュリティ要件がある企業環境で利用する場合
まとめ
NotebookLMのマインドマップ機能は、AIが自動で情報を整理・可視化し、理解を深めるプロセスを支援する強力なツールです。
特に、業務で大量の文書を扱うビジネスパーソンや、限られたリソースで効率を求める起業家、ナレッジ管理を重視する企業担当者にとって有用と言えます。
ただし、万能ではなく「自由度の低さ」や「AI精度への依存」といった制約もあるため、利用目的に応じて向き不向きを判断することが重要です。
正しく使えば、情報整理の生産性を飛躍的に高めるパートナーとなるでしょう。