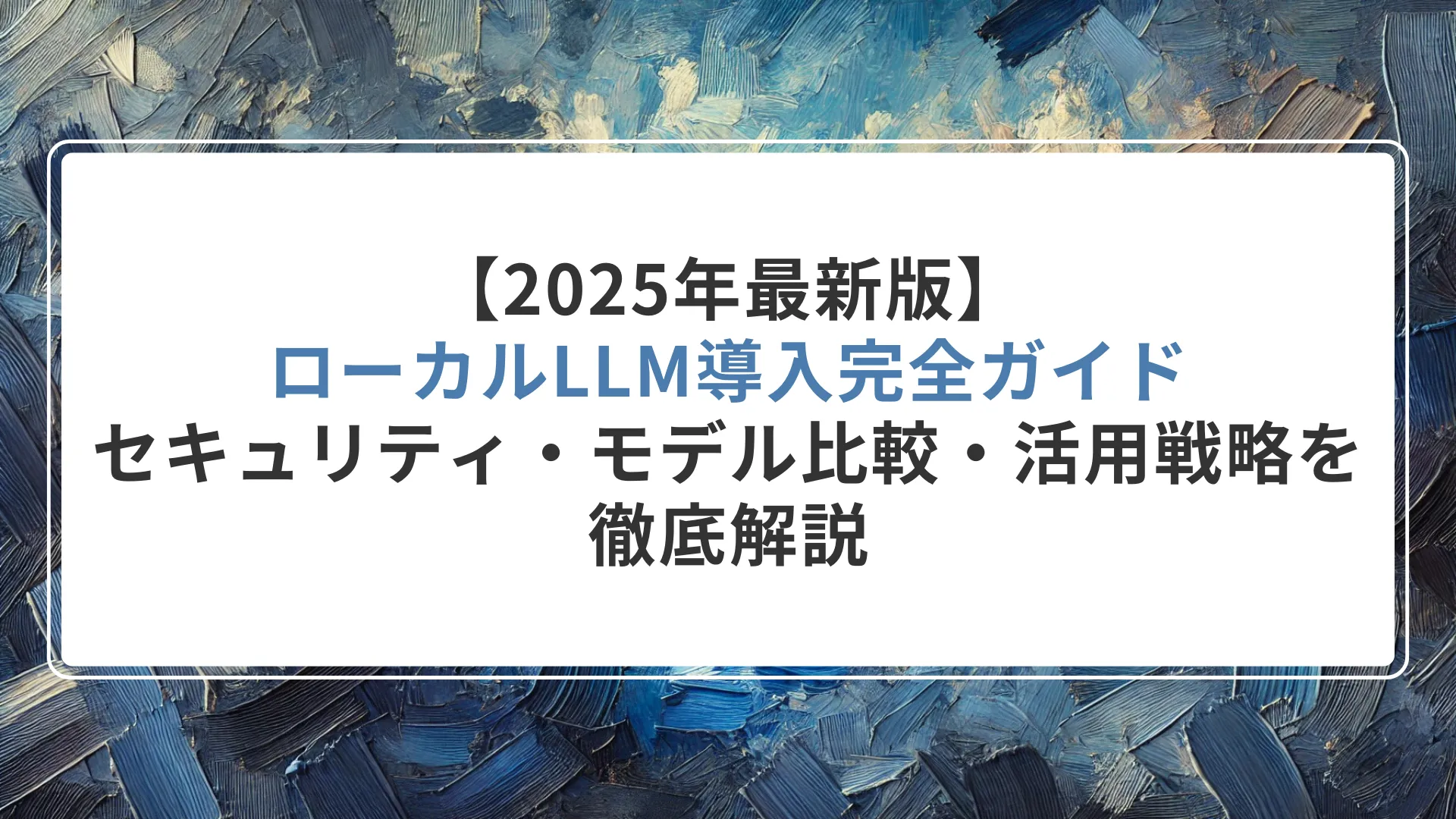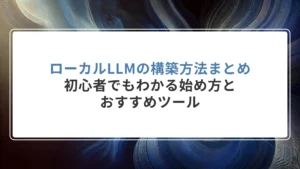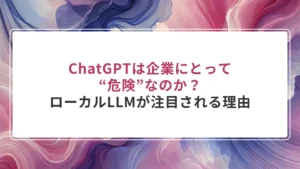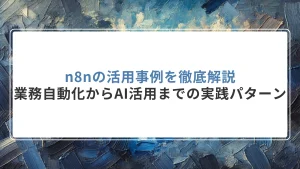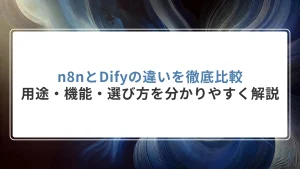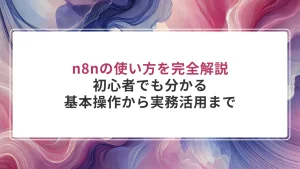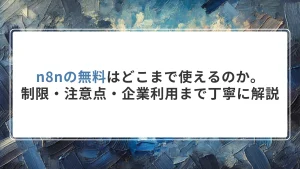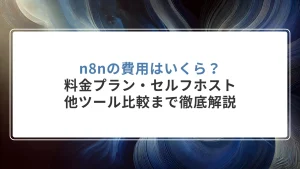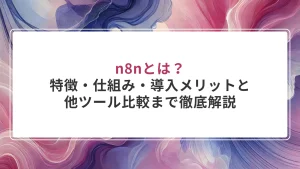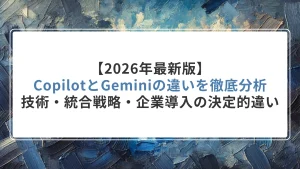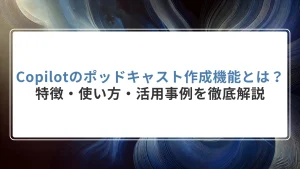生成AIがもたらす業務改革の波は、私たちの働き方に着実に浸透しつつあります。ChatGPTやGeminiといったAIツールを活用する企業が増える一方で、「社外サーバーにデータを送るのは不安だ」「機密情報をクラウドに入力していいのか」という声も根強く聞こえてきます。
このようなジレンマに直面している多くの企業にとって、今注目されている解決策が「ローカルLLM(Local Large Language Model)」です。
ローカルLLMとは、クラウドを経由せず、自社のPCやサーバー内で完結して動作する大規模言語モデルのこと。インターネットに接続しなくてもAIを稼働できるため、情報漏洩のリスクを極限まで抑えつつ、AIの恩恵を享受することができます。
本記事では、AI導入を検討する企業担当者から、スキルアップを目指すビジネスパーソン、将来のAIキャリアを描く学生まで、幅広い読者に向けてローカルLLMの全体像を解説します。
- ローカルLLMとは何か?クラウド型との違いは?
- 導入のメリット・デメリットは?
- どんなモデルやツールが使えるのか?
- 具体的な導入手順や活用事例は?
- 導入にあたっての注意点や戦略とは?
AI活用の主導権を「自社の手に取り戻す」選択肢として、ローカルLLMはますます重要性を増しています。この記事が、導入の第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
ローカルLLMとは何か?——クラウドとの本質的な違い
ローカルLLMの定義:AIを“自社内”に迎え入れるという選択
「ローカルLLM(Local Large Language Model)」とは、クラウド上ではなく、自社のPCや社内サーバーといったローカル環境で直接稼働する大規模言語モデルを指します。
この仕組みでは、AIの「脳」にあたるモデルファイルを自らのマシンにダウンロードし、インターネットを介さずに処理を完結させます。つまり、データが一切社外に出ないのです。
これは、単に“安全性の高いAI”というだけでなく、「AIとの距離感を自分たちでコントロールできる」という、本質的な自由を意味します。
クラウド型LLMとの違い:動作場所と主導権の違い
私たちが普段使っているChatGPTやGeminiは「クラウド型LLM」に分類されます。インターネット越しにアクセスし、外部の巨大サーバーでAIが動作するのが特徴です。
一方、ローカルLLMは手元の環境で直接AIが動くため、「どこで動くか」「誰が主導権を握るか」がクラウド型とは根本的に異なります。
| 比較項目 | クラウドLLM | ローカルLLM |
|---|---|---|
| 動作場所 | 外部サーバー(クラウド) | 手元のPC/社内サーバー |
| データ処理 | 外部に送信され処理される | すべてローカルで完結 |
| セキュリティ | サービス提供側に依存 | 自社で完全に管理可能 |
| カスタマイズ性 | 制限あり | 高度なファインチューニングが可能 |
| ネット接続 | 必須 | 不要(オフラインでも利用可) |
この表が示すように、ローカルLLMは“AIを外部の誰かに預ける”のではなく、“AIを自社の中に迎え入れ、育てる”というアプローチなのです。
2025年、なぜローカルLLMが注目されるのか?
このタイミングでローカルLLMの注目度が急上昇している理由は、単一の要因ではありません。以下の3つの変化が重なったことが背景にあります。
① セキュリティと規制強化の波
GDPR(EU一般データ保護規則)をはじめとした国際的な個人情報保護の潮流は、日本国内にも確実に波及しています。企業は今、入力した情報が「どこで処理されるのか」を問われる時代にいます。
ローカルLLMは、データの“出入り”を完全に自社内で閉じることができるため、最も安全で、かつ説明可能な選択肢として急速に普及しつつあります。
② モデルの高性能化と“手のひらサイズ”化
数年前まで、LLMを動かすには大規模なGPUクラスタや高額なサーバーが必要でした。しかし今では、一般的なゲーミングPCでも実用レベルのLLMを動かせる時代になっています。
たとえば「Llama 3」や「Gemma」など、オープンソースの軽量モデルが次々と登場し、技術の民主化が急速に進行しています。
③ 業務ニーズの深化と“内製AI”の模索
クラウド型の汎用モデルは便利な反面、**「うちの業務にはちょっとズレてる」**という声も少なくありません。
ローカルLLMなら、自社の専門用語や業務知識を学習させた“うちの会社だけのAI”が構築可能です。これは単なる効率化ではなく、業務知の内製化・資産化にもつながります。
ローカルLLM導入で得られる5つの価値
ローカルLLMの導入は、単なるセキュリティ対策にとどまりません。むしろそれは、「AIとの共生を、自らの手でデザインする」ための新しい道筋です。この章では、ローカルLLMが企業や個人にもたらす具体的な5つの価値を、実務に即した視点から解説します。
情報漏洩リスクを根本から遮断できる
外部ネットワークを一切経由せず、全処理がローカルで完結するという特性は、セキュリティに対して“ゼロトラスト”の理想形といえます。
特に、以下のようなシーンでその恩恵は絶大です:
- 顧客情報を扱うコールセンター
- 法務・財務部門の機密文書の作成
- 研究開発部門でのナレッジ活用
「入力内容がどこにも送信されない」という明快な構造は、社内のAI利用ガイドラインづくりにも貢献します。
応答速度が飛躍的に向上する
クラウド型LLMでは、必ず一度ネットを経由するため、応答には数秒〜十数秒の“待ち”が生じます。
しかし、ローカルLLMなら通信による待機時間がゼロ。処理スピードは“ネット速度”ではなく“PC性能”に依存します。
- 社内チャットボットの即時応答
- 大量文書の要約や分類作業の高速化
- リアルタイム翻訳や議事録生成
など、“速さが価値を生む業務”において、ローカルLLMの即応性は圧倒的な強みになります。
コストが予測可能かつ最適化しやすい
クラウドLLMは一般に従量課金制であり、使えば使うほど費用が膨らみます。
一方、ローカルLLMは:
- 初期投資(ハードウェア、モデル準備)
- 維持コスト(電力、運用人件費)
の構造が明確で、利用回数に依存しないため、長期的な予算設計が立てやすくなります。
とくに、AIを組織全体に展開したい場合や、業務利用が日常化している部署では、月額課金のクラウド型よりもトータルコストを抑えられるケースが多くあります。
オフラインでも使えるという“安心感”
地方の建設現場、工場のクローズドネットワーク、セキュアルーム、海上輸送船…。
こうしたネット接続が難しい現場においても、ローカルLLMならAIの力を最大限活用できます。
さらに、
- 災害時など通信インフラが停止した状況でも稼働可能
- オフライン研修や情報制限下での業務支援
など、“つながらない前提で使えるAI”としての信頼性が、BCP(事業継続計画)対策としても注目されています。
AIを「自社仕様」に育てられる自由度
ローカルLLM最大の強みは、モデルの中身を自由にカスタマイズできることです。
たとえば:
- 社内用語や業務フローを学習させたAI
- 特定の製品情報やFAQに特化したカスタムチャットボット
- 過去の議事録やレポートを元に意思決定を支援するAI
といった形で、“汎用AIを自社仕様に染め上げる”ことができます。
この自由度は、クラウド型のように“仕様が外部に固定されている”環境では決して得られない、ローカルならではの価値です。
ローカルLLM導入前に理解すべき3つのリスクと制約
ローカルLLMは確かに魅力的な選択肢です。しかし、導入を“成功”に導くためには、その裏側にある制約やハードルを正しく理解しておく必要があります。
この章では、特に見落とされやすい3つのデメリットについて、企業現場の実情に即して解説します。
高性能なハードウェアが“前提”になる
ローカルLLMを動かすには、AIモデルのサイズに応じた十分なGPUリソースが必要です。
- 小規模モデル(7Bクラス)でもVRAM 8〜12GBが推奨
- 中〜大規模モデルではVRAM 24GB以上が必要
一般的なノートPCでは動作しないことも多く、専用のハードウェア投資は避けて通れません。
特に、複数人で使う社内AIツールを構築する場合や、複雑な推論処理を行う場合には、NVIDIA RTX A6000やApple M2 Ultra級のハード環境が現実的な要件となるケースもあります。
性能面でクラウド型に及ばない可能性がある
ローカルLLMは日進月歩で進化していますが、やはりOpenAIのGPT-5やGoogle Gemini 2.5 Proといったクラウド超大型モデルと比べれば、その性能には差があります。
特に、以下のような高度タスクでは差が顕著になることがあります:
- 多段階の論理推論
- ユーモアや創造性を要する文章生成
- ニュース性の高い情報に基づく回答(リアルタイムWeb検索など)
つまり、すべての用途にローカルLLMが最適というわけではないという現実を、導入前に把握しておくことが重要です。
運用には“チーム内に技術者”が必要
最大の壁はここかもしれません。
ローカルLLMは、モデルの選定からツールの導入、パラメータ調整、トラブル対応、セキュリティ設定、モデル更新まで、多岐にわたる運用管理が必要です。
そのため、次のようなリソースが欠かせません:
- PythonやCLI操作に慣れた技術担当者
- ハードウェア/ドライバ管理を担うIT部門
- エラー対応や最適化ができる技術支援体制
クラウド型LLMのように「使うだけ」で済むわけではないため、「運用する覚悟と体制」も含めて導入計画を立てることが求められます。
しかし、これらの制約は“乗り越えられない壁”ではありません。
むしろ、ハードウェア要件は年々緩和され、ツールもGUI化が進み、運用知見も日々蓄積されているため、今がまさに“参入しやすくなったタイミング”とも言えるでしょう。
2025年最新版|おすすめローカルLLMモデル5選
ローカルLLMの選定は、単に「性能が高いか」だけでなく、利用目的・実行環境・習熟度によって適切なモデルが異なります。
ここでは、2025年現在注目を集めているモデルの中から、実用性・日本語対応・動作環境のバランスを重視して選び抜いた5つをご紹介します。
Gemma 3n E4B:初心者でも扱える“軽量モデルの代表格”
Googleが開発した「Gemma」シリーズの中でも、特に軽さと手軽さに特化したモデルです。
ノートPCでも動作可能なレベルでありながら、ニュース要約や簡易翻訳、会話タスクなど基本機能はしっかりカバー。導入の第一歩として最適です。
- 推奨環境:VRAM 8GB以上
- 向いている人:個人/非エンジニア/入門ユーザー
- 強み:導入が簡単、動作が軽快、日本語もある程度対応
gpt-oss-20b:“無料版GPT”の名にふさわしい高性能モデル
OpenAIが公開したオープンソース版のGPT系モデルで、論理性や創造性のバランスが非常に優秀。フリーで使えるとは思えないほど、自然で的確な応答が得られます。
ただし、その実力を引き出すには**かなりのGPUスペック(VRAM 24GB〜)**が求められるため、主に開発者や研究機関向けの選択肢といえます。
- 推奨環境:VRAM 24GB以上
- 向いている人:エンジニア/研究職/生成AIの実務活用層
- 強み:高精度な推論能力、コーディングや長文生成に強い
Llama 3 (8B):定番の“安定志向”モデル
Meta社が提供する「Llama」シリーズは、世界中で利用されているローカルLLMのデファクトスタンダード。
中でも「8B」は、性能と実行環境のバランスが非常に良く、企業の業務ユースでも使いやすいサイズ感です。情報量・ユーザー事例も豊富で、サポート面でも安心です。
- 推奨環境:VRAM 12GB以上
- 向いている人:業務導入検討中の企業/汎用利用者
- 強み:安定性、ドキュメントの豊富さ、自然な日本語対応
PLaMo翻訳:英日翻訳に特化した“国産の切り札”
日本発のAIスタートアップが開発した、英語→日本語の翻訳に特化したローカルLLMです。
特筆すべきは、「プロンプト不要でそのまま高品質な翻訳が得られる」という利便性。専門文書・技術資料・論文など、長文かつ文脈を要する翻訳でも一貫性が高いのが特徴です。
- 推奨環境:VRAM 16GB以上
- 向いている人:研究者/エンジニア/グローバル業務従事者
- 強み:翻訳精度の高さ、文脈保持能力、日本語最適化
Qwen3:CPUでも動く“ハードルの低い”実用モデル
Alibabaが開発した「Qwen3」は、GPUがなくても動作可能な数少ないモデルのひとつです。もちろん性能は控えめですが、日常的なテキスト処理や簡単なQ&Aには十分。
「まずは試してみたい」「古いPCしかない」といったニーズにも応えられる、ローカルLLMへの入口として貴重な存在です。
- 推奨環境:RAM 16GB以上(GPU不要)
- 向いている人:学生/ライトユーザー/ハードウェア制限がある環境
- 強み:インストールが簡単、動作が軽い、CPU対応
実行ツール徹底比較|Ollama vs LM Studio
ローカルLLMを使うには、モデル本体だけでなく、それを簡単に操作・実行できる“実行ツール(ランチャー)”が欠かせません。
本章では、2025年時点で主に利用されている2つの主要ツール「Ollama」と「LM Studio」に焦点を当て、それぞれの特徴や選び方のポイントをプロ視点で解説します。
Ollama:開発者・技術者に選ばれる“柔軟性重視”ツール
**Ollama(オラマ)**は、もともとコマンドライン操作を前提に設計された、軽量かつ高速な実行ツールです。エンジニアにとっては非常に扱いやすく、以下のような特徴があります。
- API連携が容易:他のAIツール(LangChain、LlamaIndexなど)との統合がスムーズ
- モデルの管理が簡潔:コマンド一行でインストール・実行が可能
- GUI版も登場:2025年夏以降は、GUIに対応したバージョンもリリースされ、一般ユーザーにも優しい設計に進化中
たとえば、以下の一文だけでLlama 3を起動可能です:
ollama run llama3
- 向いているユーザー:エンジニア/AI開発者/バックエンド設計者
- 強み:拡張性、スピード、開発用途との親和性
LM Studio:ノーコードで直感操作できる“万人向け”ツール
LM Studioは、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を備えたツールで、非エンジニアでも直感的に操作できる点が最大の魅力です。
- モデルの検索〜ダウンロード〜実行までをワンクリックで完結
- チャット形式のUIがわかりやすい
- プロンプト不要で自然に対話がスタートできる
導入のハードルが非常に低く、特に初めてローカルLLMを触るユーザーや、試験導入中の企業にとって最適な選択肢といえるでしょう。
- 向いているユーザー:ビジネスパーソン/学生/PoC中の企業担当者
- 強み:簡単な操作性、豊富なモデルライブラリ、GUIの親切設計
ツール選定の比較表
| 項目 | Ollama | LM Studio |
|---|---|---|
| 対象 | 技術者/開発者 | 一般ユーザー/非エンジニア |
| 操作性 | CLI(+GUI) | GUIのみ |
| 導入の難易度 | 中〜高 | 低 |
| 開発用途への適性 | ◎ | △ |
| カスタマイズ性 | 高い | 中程度 |
| モデルの管理 | コマンドで管理 | 画面で管理 |
MoMoのおすすめ指針
- 「業務でAIアプリケーションを構築したい」なら Ollama
- 「まずは使ってみたい、簡単に試したい」なら LM Studio
特に企業で複数人が使う環境では、LM StudioでPoC→Ollamaで開発連携という2段階導入も実践的です。
導入ステップ|ゼロから始めるローカルLLM(3ステップ)
ローカルLLMの導入は、「技術者だけの領域」ではなくなりました。適切なツールと知識があれば、PC1台で自社に最適なAI環境を構築することが可能です。
この章では、ローカルLLMの導入を3つのステップに分けて解説します。非エンジニアでも始められる構成になっているので、ぜひ実践してみてください。
ステップ1:自分のPCスペックを確認する
まず重要なのは、動かしたいモデルに応じたマシン性能があるかを把握することです。必要なスペックはモデルの規模によって大きく異なります。
| モデル規模 | 例 | VRAMの目安 | 推奨PC環境 |
|---|---|---|---|
| 小規模(軽量) | Gemma 3n E4B | 8GB〜 | ゲーミングノート/ミドルレンジGPU |
| 中規模 | Llama 3 (8B), PLaMo翻訳 | 12〜16GB | 高性能ノート/デスクトップPC |
| 大規模 | gpt-oss-20b | 24GB以上 | RTX A6000やM2 Ultra搭載PC |
| CPU利用可 | Qwen3など | RAM 16GB以上 | GPUなしでもOK |
また、ストレージについては、モデル1つで5GB〜20GB以上の容量が必要になる場合が多く、SSDで50GB以上の空き容量があることが理想です。
ステップ2:ツールとモデルをインストールする
■ Ollamaの場合(CLI+GUI)
- Ollama公式サイト から自分のOS用インストーラーをダウンロード
- インストール後、ターミナル(mac/Linux)またはコマンドプロンプト(Windows)を開く
- モデルを指定して実行:
ollama run llama3
- チャットUIが起動すれば成功。日本語入力も対応しています。
■ LM Studioの場合(GUI)
- LM Studio公式サイト にアクセスし、インストーラーをダウンロード
- 起動後、「Search」から目的のモデルを検索(例:Llama 3)
- ダウンロード後、左メニューからチャット画面を開き、モデルを選択して対話開始
これだけでローカルLLMが起動し、インターネット不要のAI環境が完成します。
ステップ3:性能確認と実用検証を行う
インストール直後は、次のようなテストから始めてみましょう:
- 「日本語で自己紹介して」と入力 → 応答速度/精度を確認
- 要約や翻訳のタスク → ビジネス利用のイメージを掴む
- Chatログを保存 → 他ツールとの連携準備
さらに、社内文書やPDFを読み込ませて回答させる「RAG(検索連携型生成)」の導入を目指すと、実務への応用が一気に現実的になります。
トラブル時のヒント
よくあるエラーと対処法をあらかじめ押さえておきましょう:
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| メモリ不足でエラー | モデルを小さくする/量子化(圧縮)を選ぶ |
| ダウンロード失敗 | ネット環境を確認/別モデルを試す |
| 文字化け | 入力言語設定 or モデルの言語対応確認 |
ローカルLLM導入の最初の壁は“知識”ではなく、“準備”と“勇気”です。 小さな成功体験を積み重ねながら、少しずつ活用の幅を広げていくことが、最も現実的な進め方です。
業界別|ローカルLLM導入の成功事例4選
金融業界の事例
金融機関では、顧客データ・取引データといった極めて機密性の高い情報を扱うため、「ローカルLLM」による導入が特に有効です。
例えば、ある地方銀行がオンプレミス環境に自社専用のLLMを構築し、「金融専門用語」「取引プロセス」に特化させた学習を施したところ、事務規定の管理業務において従来比130%の応答精度向上を達成しました。
また、他の銀行ではインターネット非接続のクローズドネットワーク上で生成AIを実証導入し、秘匿性の高いデータを安心して活用できる体制を整えています。
医療業界の事例
医療の現場は患者プライバシー保護が不可欠であり、クラウド経由でのAI活用には限界があります。そこで、院内ネットワーク内に「ローカルLLM」を導入し、電子カルテの要約や入退院サマリーの自動生成に活用した病院事例があります。ネット接続を遮断することで、安心してAIを運用できる環境が実現されています。
製造・建設業界の事例
製造・建設では自社固有の技術ノウハウや設計情報が競争力の源泉です。ある印刷関連企業では、完全オフラインのプライベートLLMを活用し、営業資料の自動生成および顧客対応の効率化に成功しており、約30%の業務時間削減を見込んでいます。建設会社でも、専門知識を学習させた建設業特化モデルを導入し、セキュアに技術情報を活用しています。
エンタメ・化学業界の事例
クリエイティブ領域や研究開発領域であっても、ローカルLLMの可能性は大きいです。エンタメ企業が、社内デザイン画像を学習させたAIを用いてデザイン案出しを行い、案の数が100倍に増加、分析業務で80%の効率化を達成しました。化学系企業では、従業員が社内向けチャットAIを活用し、約200種類の業務パターンで50%以上の効率化効果を確認しています。
これらの事例からわかるのは、ローカルLLMが「ただ安全性を満たすための技術」ではなく、業務プロセス全体を刷新し、ビジネス価値を高めるための選択肢であるということです。
導入時の注意点とよくある課題
ローカルLLM導入の道のりを成功に導くためには、甘さのない現場視点が欠かせません。ここでは注意点とよくある課題、そしてそれらを乗り越えるための戦略を示します。
IT担当者が躊躇する5つの理由
- 自社運用への不安:サーバー管理、モデル更新、障害対応といった運用責任が自社に帰属するため、経験のないIT部門では尻込みしがち。
- モデル選定の難しさ:多数のモデルが存在する中で、自社要件・ハードウェアに最適なものを選ぶのは容易ではありません。
- セキュリティ体制を自社で構築:クラウドならベンダーがある程度担保するところを、自社で設計・運用するプレッシャーが大きい。
- 経営層への説明責任:初期投資が大きいケースもあり、ROI(投資対効果)をどう示すかは経営判断の焦点になります。
- 技術的完成度への懸念:クラウド型最先端モデルとの性能差を懸念する声もあり、「本当に満足できるのか?」という問いが常に付きまといます。
よくあるトラブルと対処法
- メモリ(VRAM)不足エラー:モデルを読み込めないというエラーが頻出。対処法として「より軽量モデルに切り替える」「量子化(モデル圧縮)を試す」などがあります。
- 互換性・依存関係の問題:GPUドライバやライブラリのバージョンが合わず動作しないという事例も。公式ドキュメントに沿って環境構築することが肝要です。
- パフォーマンスの低下:応答速度が遅い/動作が不安定というケースでは、モデルのサイズが過大であるか、GPU負荷が限界に達している可能性があります。「別モデル検討」「ハードウェア増強」の検討が必要です。
継続的な運用のポイント
- モデルのアップデート体制:AIモデル、ツール、ライブラリの更新が継続的に行われるため、スムーズに切り替えられる体制を整えること。
- セキュリティパッチ適用:OS・GPUドライバ・ネットワーク等、関連するインフラ全般に対して定期的なセキュリティメンテナンスが必要です。
- 社内サポート体制の構築:ユーザーからの問い合わせや活用支援を行う「社内AI推進チーム」を設置することで、活用の定着と形骸化の防止につながります。
ローカルLLMとクラウドLLMの使い分け戦略
ローカルLLMとクラウドLLMを、どちらか片方だけで済ませるのではなく、“賢く使い分ける”視点こそが現代のAI活用には不可欠です。
それぞれに適した用途
- ローカルLLMが適している場面
- 機密性の高いデータ(顧客情報、法務・財務データ)を扱う場面
- オフライン/通信制限された環境(工場、建設現場、船舶内など)
- 高速応答が必要な処理(社内チャットボット、リアルタイム要約)
- 自社独自の知識・ナレッジを学習させて内部専用AIを構築したい場合
- クラウドLLMが適している場面
- 創造的な文章生成や、最新情報を反映した回答に依存する場面
- 初期投資を抑えて素早く試験導入したい場合
- 運用負荷をできるだけ低くしたい、またはスケール変動が大きい用途
ハイブリッド運用のススメ
最も現実的かつ柔軟なのは、ローカルとクラウドをハイブリッドで運用する戦略です。例えば:
- 日常的な社内問い合わせや文書要約はローカルLLMでセキュアに運用
- 外部向けチャットボットやクリエイティブ生成部分はクラウドLLMで拡張
- 質問内容をまず軽量ローカルモデルで処理し、複雑なケースだけをクラウドに振る「ルーティング型」も有効です。
このような棲み分けによって、コスト、セキュリティ、運用負荷の最適なバランスを実現できます。
まとめ
本記事では、今注目の「ローカルLLM」について、基礎知識、メリット・デメリット、導入ステップ、おすすめモデル、ツール比較、事例、注意点、そしてクラウド型との戦略的使い分けまで、包括的に解説しました。
ローカルLLMは、「セキュリティ」「コスト」「カスタマイズ性」という、かつてクラウド型が抱えていた課題を根本的に改善する力を持っています。特に、機密情報を扱う企業や、オフライン環境での利用が求められる場面において、その価値は飛躍的です。
もちろん、導入にはハードウェアの準備や専門的な運用体制というハードルも存在します。しかし、2025年の現在、軽量化されたモデル、使いやすくなったツール、豊富な情報が手元にあります。すなわち、導入の敷居は確実に下がっています。
ローカルLLMの導入を成功させるためには、以下の3つを意識してください:
- 目的の明確化:何を解決したいのか、どの業務のどの部分を改善したいのかを明らかに。
- スモールスタート:まずは特定の部署・用途から導入し、成功体験を積み重ねること。
- 適切なツールとモデルの選定:自社のスキル・環境・用途にフィットするものを選び、無理をせず段階的に活用を拡大する。
AI時代において、「主導権を自社の手に取り戻す」という意味で、ローカルLLMは極めて重要な選択肢です。このガイドが、皆さまがその第一歩を踏み出す支えになれば、私たちMoMoとしても嬉しく思います。
セキュリティ要件に応じた構成設計、モデル選定・カスタマイズ、導入支援、さらには社内教育まで、“あなたの会社専用AI”を共に作るパートナーとして対応しております。
📩 お見積もり・ご相談は以下のボタンからお気軽にどうぞ。