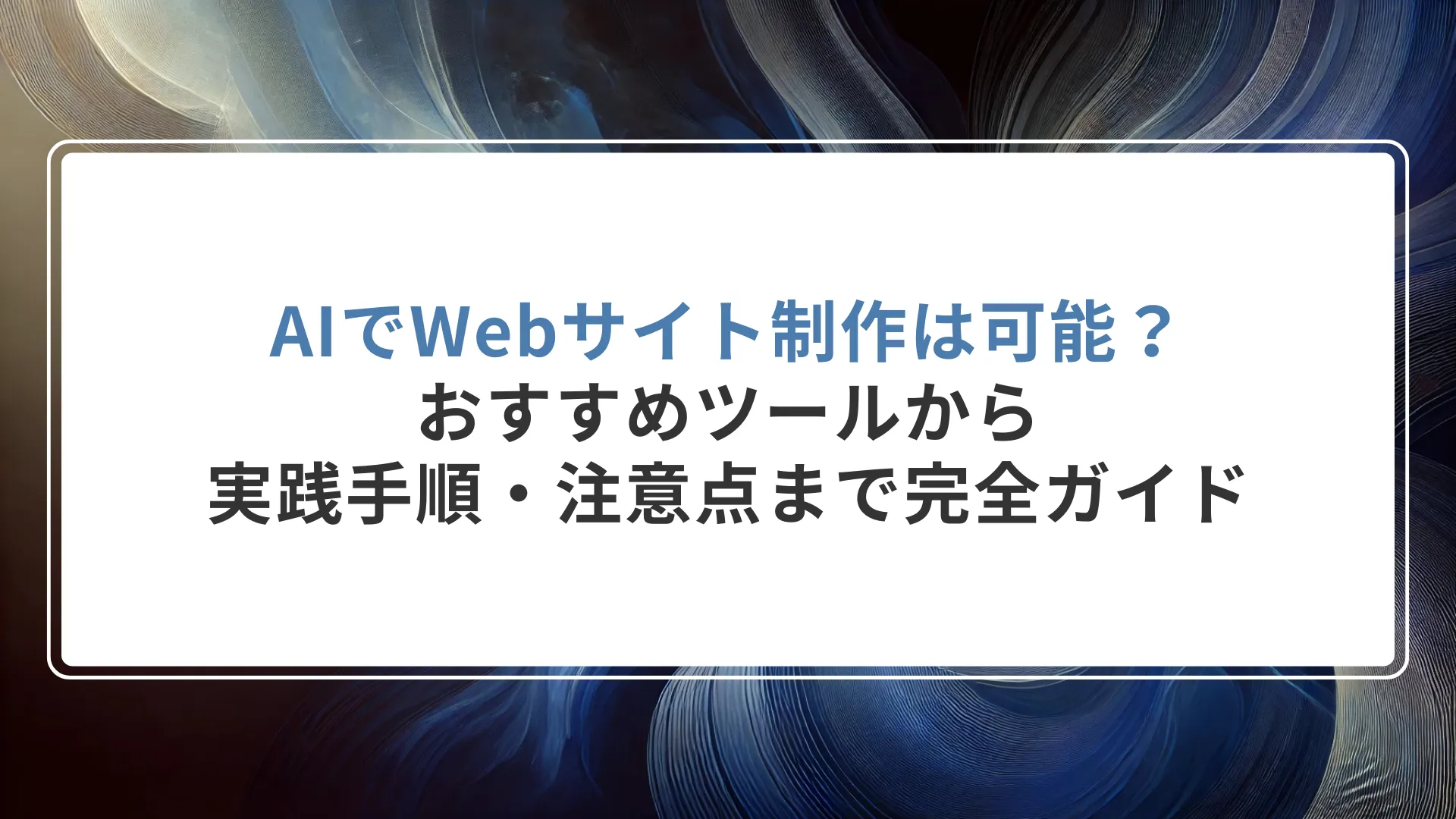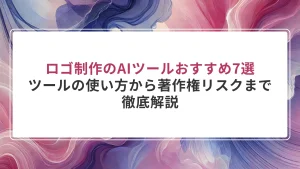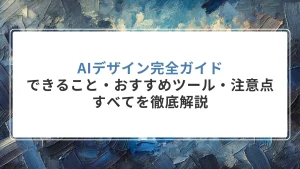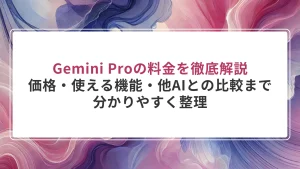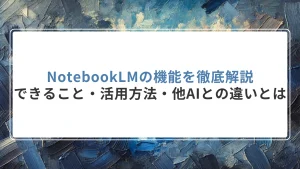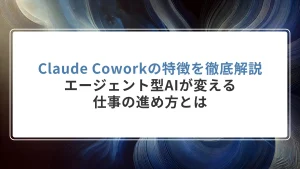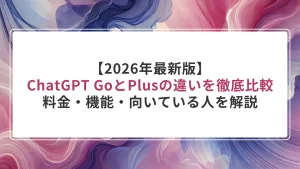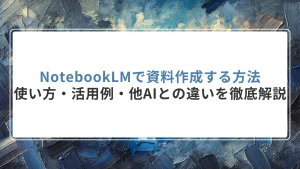企業や個人にとって「Webサイト」は名刺以上に重要な存在です。
かつては専門的なプログラミングやデザインの知識が不可欠で、制作には数十万円〜数百万円の費用と数週間以上の期間を要することが一般的でした。
しかし近年、生成AIの進化によってこの常識が変わりつつあります。
「AIでWebサイト制作ができるのか?」 という問いは、多くのビジネスパーソンや起業家にとって現実的な選択肢となってきました。
実際に、WixやWordPress.comをはじめとするAI搭載のWebサイトビルダーは、数分〜数時間でプロ並みのサイトを生成できるようになっています。しかも、文章、画像、レイアウト、SEO設定まで含めて自動化されるケースもあり、従来の外注依存から内製化への流れを強力に後押ししています。
とはいえ、AIに全てを任せれば済むというわけではありません。効率性やスピードの裏で、ブランド独自性や法務・セキュリティの課題も浮き彫りになっています。
この記事では、AIのWebサイト制作はどこまで可能なのかを整理し、おすすめツールや実践手順、導入時の注意点を網羅的に解説していきます。
AIでWebサイト制作は本当に可能か?【できること・できないこと】
AIによるWeb制作はすでに現場で実用化されています。とはいえ、万能ではなく「できること」と「まだ難しいこと」が存在します。ここでは整理してみましょう。
AIで「できること」
- 初期サイトの自動生成
ブランド名・業種・目的を入力するだけで、ページ構成・デザイン・配色を提案。 - テキストコンテンツの生成
AIコピーライター機能で、キャッチコピーや商品説明、CTA文言を自動作成。SEOを意識した文章生成も可能。 - 画像やビジュアルの作成
ロイヤリティフリーの素材検索に加え、生成AIでオリジナルのアイコンやイラストを生成可能。 - コード自動生成・編集
HTML・CSS・JavaScriptのコードをAIが自動で書く。簡単な修正指示も自然言語で可能。 - レスポンシブ対応の最適化
スマホ・タブレット表示の自動調整機能が標準装備されているツールが多い。
AIでは「まだ難しいこと」
- ブランド独自性の完全再現
AIが生成するデザインは、過去のテンプレートや既存データに依存するため、似通った仕上がりになりやすい。 - 複雑な機能開発
会員制システム、独自データベース連携、複雑なEC機能などはAIだけでは不十分。専門的な開発が必要。 - 高度なUXデザインの実装
ユーザー心理や行動に基づいた体験設計は、人間の戦略思考が不可欠。 - 公開後の運用・セキュリティ管理
サイト生成後のセキュリティ更新やパフォーマンス最適化は、AI任せにできない領域。
おすすめAI Webサイト制作ツール7選
「AIでWebサイト制作できるの?」と考える多くの人がまず気になるのは、具体的にどのツールを使えばよいかです。
ここでは、2025年時点で注目されているAI搭載Webサイトビルダーを7つ紹介し、それぞれの特徴・メリット・デメリットを整理します。
Wix ADI(Artificial Design Intelligence)

- 特徴:質問形式で業種や目的を答えるだけで、AIが自動でデザインと構成を生成。
- 強み:豊富なテンプレートとアプリ連携、初心者でも即日公開可能。
- 注意点:細かいカスタマイズや高度な機能は制限あり。
👉 おすすめ対象:小規模事業者、個人サイト、スピード重視のユーザー
WordPress.com AI Website Builder
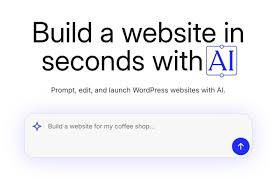
- 特徴:WordPress公式のAIビルダー。入力内容に基づきレイアウト、文章、画像を自動生成。
- 強み:世界最大級のCMS基盤に直結。拡張性が高く、ブログやECへの展開が容易。
- 注意点:プラグインやテーマ選定には学習コストが必要。
👉 おすすめ対象:長期的に運用したい企業、ブロガー、コンテンツマーケ担当
Durable AI

- 特徴:最短30秒でWebサイトを自動生成することを売りにしたスピード特化型。
- 強み:個人事業主やフリーランスがすぐにポートフォリオやサービス紹介サイトを公開できる。
- 注意点:デザインの自由度が低く、差別化が難しい。
👉 おすすめ対象:スピード重視のスタートアップ、テストマーケティング
Hocoos
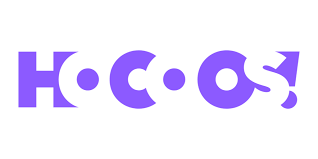
- 特徴:ビジネスに関する質問に答えると、文章やデザインを一括生成。EC機能や予約管理機能も標準装備。
- 強み:中小企業向けのバックエンド機能が充実。
- 注意点:多機能ゆえ、初心者にはやや複雑に感じることも。
👉 おすすめ対象:サービス業の中小企業、店舗運営者
10Web

- 特徴:AIがWordPress環境でサイトを自動生成。高度なSEO・Eコマース機能も搭載。
- 強み:拡張性が高く、エンタープライズにも対応可能。
- 注意点:料金は比較的高め、運用知識があると効果的。
👉 おすすめ対象:中堅〜大企業、Webマーケチーム
HubSpot CMS + AI

- 特徴:AIでページやコンテンツを生成しつつ、CRMやマーケティング機能と連携可能。
- 強み:サイトを営業・マーケティング活動と直結させられる。
- 注意点:本格利用には有料プランが必須。
👉 おすすめ対象:成長志向の企業、マーケティング強化を狙う事業者
Jimdo AI Website Builder

- 特徴:シンプルな質問に答えるだけでサイトを生成。ドラッグ&ドロップ編集も簡単。
- 強み:直感的操作、リーズナブルな価格設定。
- 注意点:デザインの多様性や拡張性は限定的。
👉 おすすめ対象:個人サイト、フリーランス、小規模店舗
AI Webサイト制作ツール比較表(2025年版)
| ツール名 | 特徴 | 強み | 注意点 | 推奨ユーザー |
|---|---|---|---|---|
| Wix ADI | 質問形式で自動生成 | 豊富なテンプレート、初心者向け | カスタマイズに制限 | 小規模事業者 |
| WordPress.com AI | レイアウト・文章自動生成 | CMS基盤と拡張性 | 学習コストあり | 企業・ブロガー |
| Durable AI | 最短30秒で生成 | スピード特化 | 独自性が弱い | スタートアップ |
| Hocoos | EC・予約管理機能統合 | 中小企業の業務連携 | 多機能で複雑 | SME/店舗 |
| 10Web | WordPress上で自動生成 | 高度SEO/EC機能 | 料金高め | 中堅〜大企業 |
| HubSpot + AI | CRMと連携可能 | 営業・マーケと直結 | 有料プラン必須 | 成長志向企業 |
| Jimdo | シンプル操作 | 低価格、初心者でも簡単 | デザイン多様性が低い | 個人・小規模 |
AI Webサイト制作の実践手順【3ステップ】
AI搭載Webサイトビルダーは「質問に答えるだけで完成」と宣伝されることが多いですが、実際に成果を出すためには 戦略的な入力と人間の調整 が不可欠です。ここでは、誰でも実践できる3つのステップをご紹介します。
ステップ1:戦略的インプットを準備する(人間主導)
AIが生成するWebサイトの品質は、最初に入力する情報の質に大きく左右されます。
以下の要素を明確にしてからツールに入力しましょう。
- サイトの目的:集客/EC販売/ポートフォリオ/採用ページなど
- ターゲットユーザー:顧客層(例:20代女性、BtoBの経営者層)
- ブランドイメージ:シンプル、信頼感、革新性、親しみやすさなど
- キーワード:SEOを意識した主要キーワードを事前に定義
👉 これらを事前に整理することで、AIの出力が「汎用的なサイト」から「戦略的に役立つサイト」へ近づきます。
ステップ2:AIによる自動生成と初期サイトの確認
準備した情報を入力すると、AIが短時間でWebサイトを生成してくれます。
この段階で注目すべきポイントは以下です。
- レイアウトの適切性:ユーザーの行動導線が分かりやすいか
- 文章のトーン:ブランドに合っているか
- 画像や色使い:ビジュアルがターゲットに響くか
- SEO初期設定:メタディスクリプションや見出しが自動最適化されているか
AIの強みは「短時間で試作品を見せられること」。この初期生成サイトを「ドラフト」として扱い、関係者や顧客に見せながら改善の議論を進めましょう。
ステップ3:人間による調整と差別化(共創フェーズ)
AIが作ったサイトは効率的ですが、そのままでは「他社と似たサイト」になるリスクがあります。
差別化を図るためには以下の作業が重要です。
- コンテンツのリライト:AI生成文を自社の言葉に置き換える
- 独自画像・動画の追加:ブランド写真やオリジナル素材を組み込む
- CTA(行動喚起)の最適化:ユーザー心理を踏まえてボタン配置や文言を調整
- UXテスト:複数デバイスで表示速度・操作性を確認
👉 AIの役割は「スピード」と「効率性」、人間の役割は「独自性」と「戦略性」。この両輪を組み合わせることで、ビジネスに本当に役立つWebサイトが完成します。
導入時の注意点とリスク管理
AIでWebサイトを制作するメリットは非常に大きい一方で、導入にあたっては見落としがちなリスクも存在します。ここでは代表的な3つのリスクとその対策を整理します。
著作権・ライセンスリスク
AIが生成するテキストや画像には、著作権の帰属や商用利用の可否に不確実性が伴う場合があります。
特にフリー版のツールでは「非商用利用のみ」とされるケースもあり、そのまま企業サイトに使うと法的リスクにつながります。
✅ 対策
- 商用利用が明示されているツールを選ぶ(Wix、WordPress.comなど)
- 生成物をそのまま使わず、自社で編集・修正して「創作的寄与」を明確にする
- 必要に応じて画像素材は有料ライセンスやオリジナル撮影素材を利用する
テンプレート依存による差別化の欠如
AIは過去のデータやテンプレートに基づいてデザインを作るため、「似たようなサイト」になりがちです。
競合と同じツールを使った結果、外観がほとんど同じになるという課題は多く報告されています。
✅ 対策
- AI出力をあくまで「下書き」として扱う
- コンテンツやビジュアルを自社独自のものに置き換える
- デザインシステム(ブランドカラー・UIルール)を先に定義して反映させる
運用・セキュリティの課題
AIは制作段階を効率化しますが、運用やセキュリティ管理は人間の責任範囲です。
自動生成されたまま公開したサイトが、更新されずに脆弱性を抱えたまま放置されるリスクもあります。
✅ 対策
- 公開後は必ずセキュリティ更新を実施
- Core Web Vitals(表示速度・安定性)を定期的にチェック
- 専門家に保守契約を依頼するか、社内で運用体制を整える
コンプライアンス・ブランド一貫性
AI生成の文章は便利ですが、社内のコンプライアンスやブランドトーンに沿わない内容が出力されることもあります。
✅ 対策
- 社内ガイドラインをAI入力の前に定義
- 生成後は必ず人間がレビューして修正
- ブランドトーンを反映できるよう、AIに具体的な指示を与える
以上のリスクを踏まえると、AIは「人間の代替」ではなく「効率化のパートナー」として扱うことが重要です。
まとめ:AIと人間の共創によるWeb制作戦略
この記事では「AIでWebサイト制作は可能か?」というテーマのもと、できること・できないこと、主要ツール、実践手順、注意点を解説しました。
最後に、読者が押さえるべきポイントと今後の戦略を整理します。
本記事の要点整理
- AIでできること
サイト構成、デザイン、文章、画像生成、SEO初期設定など → 初期制作の効率化に最適 - AIでは難しいこと
ブランド独自性の再現、複雑な機能実装、UX戦略、公開後の保守 → 人間の戦略と運用が不可欠 - おすすめツール
- Wix ADI:初心者向けスピード重視
- WordPress.com AI:長期運用・拡張性
- Durable AI:最短30秒で立ち上げ
- Hocoos:中小企業向けEC・予約機能
- 10Web:高度SEO+拡張性
- HubSpot CMS + AI:CRM連携による成長戦略
- Jimdo:個人・小規模事業者に最適
- リスクと対策
著作権/テンプレート依存/運用管理/コンプライアンス → 「AI出力を下書きとし、人間が最終調整」することで解決
今後のWeb制作におけるAI活用戦略
- AIを初期制作の加速装置として活用する
- 速さとコスト削減を最大限に活かし、仮説検証やテストマーケティングに投入する。
- 人間が差別化とブランド戦略を担う
- コンテンツのリライト、独自ビジュアル、UX設計を通じて「他にはないサイト」を作る。
- 運用と品質管理を重視する
- Core Web Vitalsやセキュリティ対策を定期的に実施し、AIの効率性と人間の品質管理を両立させる。
読者への提言
「AIでWeb制作できるか?」という問いに対する答えは、Yes、ただしAI単独では不十分 です。
最適なアプローチは、AIを効率化のパートナーと位置づけ、人間が戦略と独自性を担保すること。
AIを上手に活用すれば、Web制作は「コスト削減」だけでなく「市場投入のスピード」「ブランドの柔軟な進化」に直結する強力な武器となります。
2025年以降、Web制作においてAI活用は標準化していくことが確実です。今こそ、自社の戦略に合わせたAI導入の第一歩を踏み出すべきでしょう。