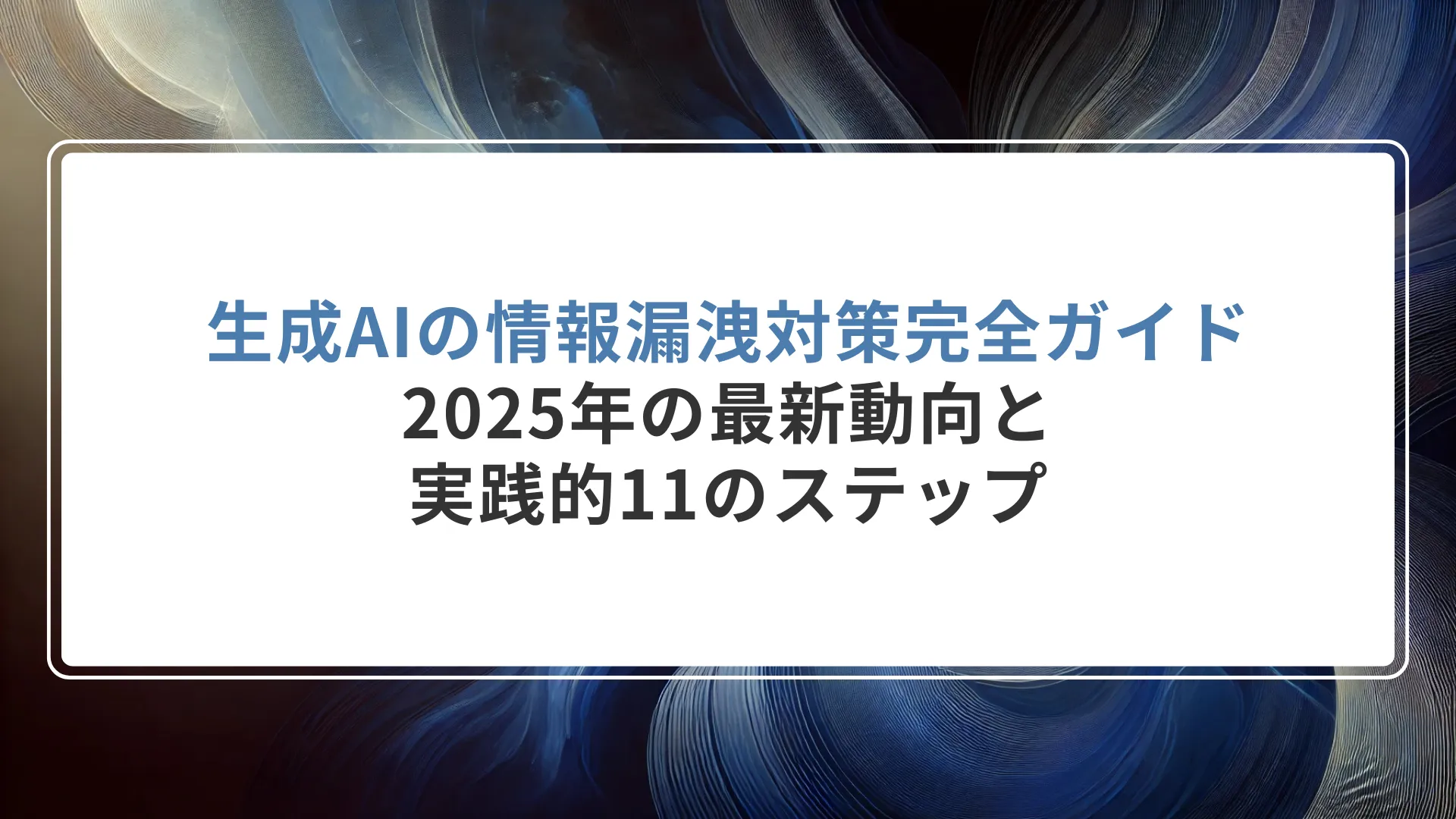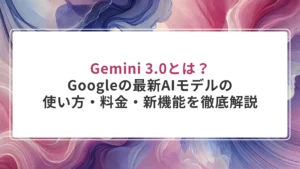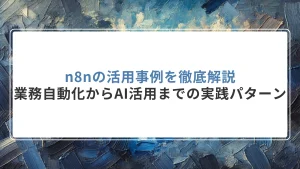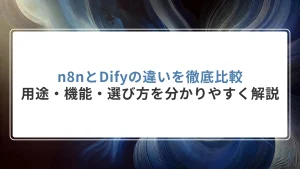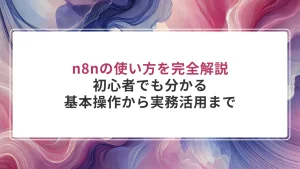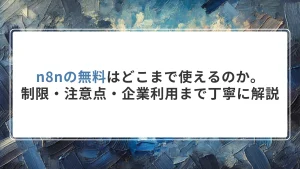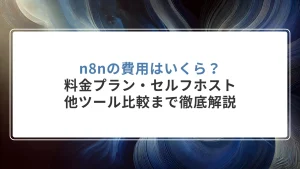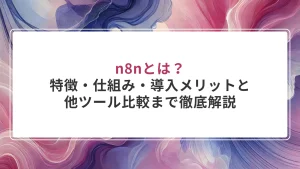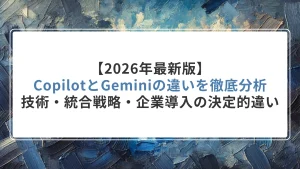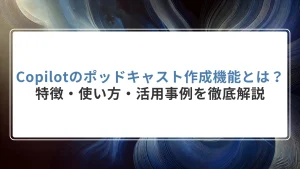生成AIは、ビジネスの生産性を大きく引き上げる可能性を持ちながら、同時に“情報漏洩”という深刻なリスクを併せ持っています。例えば「機密データを ChatGPT に入力してしまった」「AIツールを通じて顧客情報が社外に流出してしまうのではないか」といった懸念を持つ企業担当者は少なくありません。実際、2025年にはAI関連のセキュリティインシデントが顕在化しており、被害を受けた企業も報告されています。とはいえ、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、生成AIを安全かつ効果的に活用する土台は十分に整えられます。本記事では、生成AIによる情報漏洩のメカニズム、2025年の最新事例、さらに企業が即実行できる11のAIの情報漏洩対策までを体系的に解説します。本稿を読み終える頃には、御社の状況に応じた最適なセキュリティ戦略を検討できるようになるでしょう。
生成AIの情報漏洩とは?基礎知識を整理する
生成AIを業務に取り入れる際、まず押さえておきたいのが“どのように情報漏洩が起こり得るのか”というメカニズムです。ここでは、「入力データ」「クラウド保存」「アクセス権限」という3つの観点から解説します。
生成AI利用時の情報漏洩メカニズム
生成AIサービス(特に無料版や広く公開されたもの)では、ユーザーが入力した内容がモデルの学習データとして再利用されるケースがあります。つまり、機密情報や個人データが意図せず他ユーザーの回答生成に使われる可能性があります。
加えて、入力されたデータはサービス提供者のクラウドサーバー等に保存されるため、提供者のセキュリティ体制次第では「不正アクセス」や「内部犯行」による漏洩リスクが生じます。さらに、AIツールに社内データベースやファイルサーバーへのアクセス権限が与えられている場合、その権限が適切に制御されていなければ、本来アクセスすべきでない情報までもが学習・出力されてしまう怖れがあります。
企業が直面する3つの主要リスク
これらを踏ま、企業が直面しうる代表的リスクを整理します。
| リスクの種類 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 入力情報の漏洩 | 従業員が機密情報を生成AIに入力し、学習データとして流用されるリスク | 会議議事録・ソースコード・顧客情報等をChatGPT等に入力し、他ユーザーの回答に含まれる |
| アカウント情報の流出 | 生成AIサービスのアカウントが乗っ取られ、過去利用履歴・入力情報が閲覧される可能性 | パスワードの使い回し/マルウェア感染によるログイン情報漏洩 |
| システム障害・脆弱性 | AIサービス自身のバグや設計上の欠陥によって、ユーザーのデータが漏洩する | 提供側サービスに脆弱性があり、他ユーザー情報が閲覧可能になったケース |
これらのリスクは、企業の信頼性・競争力を大きく損なう可能性があります。次章では、2025年最新の情報漏洩事例を通じて、現実にどのようなケースが起きているかを具体的に見ていきます。
【2025年最新】生成AIの情報漏洩の実際の事例
理論だけでは捉えきれないリスクを、実際に発生した事例から学びましょう。以下は、2025年に報じられた代表的な生成AI・情報漏洩インシデントです。
IBM報告:AIモデル・アプリケーションの13%が侵害(2025年7月)
IBM社の報告によると、2025年時点で「AIモデルまたはアプリケーションの侵害を経験した組織が13%」に上るとされています。さらに、侵害経験のある企業のうち97%が「適切なAIアクセス制御を欠いていた」と報告しています。
このデータは、生成AI・AIアプリケーション導入が急速に進む一方で、ガバナンス(AIガバナンス)やアクセス制御が追いついていない現状を明らかにしています。
AI活用サイバー攻撃の急増(2025年)
2025年には、生成AIを悪用したサイバー攻撃が明確に増加しており、分析では「AI支援サイバー攻撃インシデントが72%増加」し、世界的な被害額は300億ドル超とも報じられています。
また、ある報告では「約16%のサイバー事件が生成AIを用いた攻撃内容であった」と指摘されています。
こうした動きは、生成AIが単なる効率化ツールではなく、新たな“攻撃手法”としても悪用可能な存在になっていることを示しています。
シャドーAI/影のAI利用によるリスク
「シャドーAI(企業が把握していない従業員のAIツール利用)」も深刻な課題です。あるデータでは、「20%の組織がシャドーAI関連のインシデントを経験している」と報告されており、平均漏洩コストも約463万ドルに上るとされています。
このように、公式ルートでは管理されていないAI利用が、情報漏洩の“隙”を生みだしています。
(※注:個別企業名、年月、被害状況のディテールについては、公表されていないケースも多く、詳細は限られたものに留まります)
生成AIの情報漏洩が発生する4つの原因
実践的に対策を講じるためには、「なぜ生成AIを起点とした情報漏洩が起こるのか」を構造的に理解することが重要です。ここでは、4つの視点から原因を整理します。
ユーザー側の要因
最も典型的なのが、利用者自身に起因するヒューマンエラーです。
- 機密情報を生成AIに入力してしまう(例:ソースコード、顧客データ、会議記録)
- セキュリティ意識が低く、「ちょっとだけなら」という思考で行動してしまう
- シャドーAIの存在:企業が許可していないAIツールを従業員がプライベート利用・業務利用しており、管理外のまま機密データが流用される
サービス提供側の要因
ユーザー側の制御を超えて、サービス提供者の問題が漏洩を招くことがあります。
- システムの脆弱性:設計欠陥・バグによる漏洩リスク
- セキュリティ対策・アクセス制御・暗号化などが不十分な体制
- データ利用ポリシーや保存場所・学習利用の透明性が欠けている
外部攻撃/サイバー脅威
第三者による攻撃は、生成AI時代においても主要な原因です。
- マルウェア感染:従業員端末に侵入し、AIサービスのアクセス情報を盗む
- フィッシング攻撃:生成AIを使ったフィッシングメールや偽チャットボットを用いた認証情報窃取
- サプライチェーン攻撃:例えば、AIツールと連携する外部サービスの侵害を通じて社内データにアクセスされる事例
生成AI特有の構造的要因
生成AIには、従来のITシステムとは異なるリスク構造があります。
- 広範なアクセス権限:生成AIは多数のデータソースと連携する傾向があり、万が一侵害されると被害範囲が大きくなります。
- 信頼を前提としたアーキテクチャ:多くの企業が「AIは信頼できるアシスタント」という前提で導入を進めており、その信頼が裏切られた場合の影響が甚大です。
- 機密性判断の欠如:現状の生成AIには「これは公開可能なデータ/これは機密データ」という判断能力が備わっておらず、入力されたデータがそのまま出力に含まれてしまうケースがあります。
企業が実施すべき11のAIの情報漏洩対策
リスクを理解したなら、次は実践です。ここでは、企業が取るべき対策を「基本対策」「技術的対策」「運用・管理対策」の3つのカテゴリに分け、合計で11のステップを紹介します。
基本対策(必須)
まずは、生成AIを安全に扱うための社内基盤を整えることが第一歩です。ツールを導入する前・導入直後に取り組むべきものです。
対策1:社内ガイドラインの策定と周知
生成AIの利用ルールを明確化し、全従業員に徹底する。特に以下の項目を含めるべきです:
- 利用許可するAIツールのリスト(企業として安全性を確認済みのもの)
- 入力禁止情報の明確な定義(例:顧客名、電話番号、メールアドレス、マイナンバー、未公開の売上データ、設計図、ソースコード)
- 違反時の報告・罰則規定
対策2:機密情報の入力禁止ルールの徹底
「何が機密情報か」を曖昧にせず、具体的に列挙して入力禁止とする。曖昧な表現では判断が分かれ、漏洩リスクが残ります。
対策3:データ学習オプトアウト設定の実施
生成AIサービスでは、ユーザーが入力データをモデル学習に使われないようオプトアウトできる設定がある場合があります。例えば、ChatGPTでは「Chat history & training」をオフにすることで、対話履歴が学習に利用されないようにできます。
企業が従業員に個人アカウント利用を許可する場合は、この設定を義務付けることが最低限の防衛策です。
技術的対策(推奨)
基本ルールだけでは防ぎきれない生成AI特有・サイバー攻撃特有のリスクに対しては、技術的な仕組みを整えることが重要です。
対策4:企業向けAIサービスの導入
可能な限り、個人向け無料サービスではなく、セキュリティ・管理機能が強化された企業向け生成AIサービスを導入してください。これには以下の点が含まれます:
- 入力データが学習に利用されないことを契約で保証しているか
- 管理コンソール・監査ログ・SSO連携等が提供されているか
例:ChatGPT Enterprise/Team、Microsoft Copilot for Microsoft 365、Google Gemini for Workspace 等
対策5:API版の活用
自社システムに生成AI機能を組み込む場合、Web UI版ではなくAPI経由での利用が推奨されます。多くのサービスでは、API経由のデータはデフォルトでモデル学習に利用されないポリシーとなっています。
対策6:アクセス権限の適切な管理
生成AIツール・連携先サービスへの「データアクセス権限」は最小権限原則(Least Privilege)に基づき付与することが不可欠です。
これにより、万が一アカウントが乗っ取られた場合でも、被害範囲を限定できます。
対策7:ローカルLLM(オンプレミスAI)の導入
最もセキュアな選択肢の一つが、クラウドではなく自社サーバーやPC上で動作する生成AI(ローカルLLM)を導入することです。
メリット:
- データが外部サーバーに送信されない
- モデル学習に利用される心配がない
- 業務・業界特化のカスタマイズ可能
ただし、初期コスト・ハードウェア・運用ノウハウが必要となります。
対策8:セキュリティツールの導入
生成AI連携環境には次のようなセキュリティツールも有効です:
- DLP(Data Loss Prevention):機密情報がAIサービスに送信されるのを検知・ブロック
- CASB(Cloud Access Security Broker):誰がどのクラウドサービス(生成AI含む)を使っているかを可視化・制御
運用・管理対策(重要)
ルール・ツールを整備しても、それを運用・継続改善しなければ意味が薄れます。以下のステップを継続的に行うことが、生成AI時代の情報漏洩対策には不可欠です。
対策9:アカウントセキュリティの強化
- 強固なパスワード(長く、複雑、使い回しなし)の義務化
- 二段階認証(2FA/MFA)の必須化
この基本を徹底するだけでも、不正ログインによる被害リスクを大幅に軽減できます。
対策10:従業員教育とリテラシー向上
ガイドラインや技術仕様だけではなく、従業員一人ひとりが生成AI時代のリスクを理解し、自律的に行動できるように教育することが重要です。定期的に最新の情報漏洩事例やフィッシング対策、社内ルールの再確認をテーマに研修を実施してください。
対策11:監視とインシデント対応体制の構築
- どの社員が、いつ、どの生成AIサービスを、どのように利用しているかを可視化・監視する仕組みを整える
- 万が一情報漏洩インシデントが発生した場合に備え、①被害拡大防止(アカウント停止など)②原因調査③影響範囲特定④監督官庁・顧客への報告⑤再発防止策の策定と実行、という流れを事前に定め、訓練を行っておくこと
業種別・規模別の対策優先順位
すべての企業が、上記11項目を一度で完全に実施するのは現実的ではありません。企業の業種・規模・予算・扱うデータの性質に応じて、優先順位をつけることが現実的かつ効果的です。
中小企業向けの優先アプローチ
リソースが限られている中小企業では、以下の順で進めるのが現実的です。
- 最優先:対策1/2/3(ガイドライン策定・機密情報入力禁止・データ学習オプトアウト)
- 次点:対策9/10(アカウントセキュリティ強化・従業員教育)
- 検討段階:対策4(企業向けサービス導入)・対策7(ローカルLLM導入)
まず“ルール”を明確化し、“人の意識”を高めることから着手することで、低コストで効果を出しやすいです。
大企業向けの包括的アプローチ
大規模組織では、より体系的かつ構造的な対策が求められます。
- 必須:対策1〜11すべてを計画的に実施
- 特に重視すべき:対策4(企業向けサービスの全社導入)、対策7(ローカルLLMの検討・導入)、対策8(DLP/CASBによる監視・制御)、対策11(インシデント対応体制の強化)
大量の従業員、大規模なデータ、複数の関連システムを抱える大企業では、個別対応ではなく“仕組み+運用”として全社に浸透させることが鍵です。
業種別の注意点
取り扱うデータの性質に応じて、特に注意すべきポイントが異なります。
- 金融業:顧客個人情報・取引情報・クレジットデータ等、高度な機密性を伴うため、ローカルLLMの導入や閉域網環境でのAI運用を強く推奨。
- 製造業:設計図・技術仕様・研究開発情報など知的財産が主。サプライチェーン連携も多いため、サプライチェーン全体でのAI利用ルール策定と連携監査が鍵。
- IT業:ソースコードそのものが貴重な資産。従業員が生成AIにコードを入力してしまうと企業競争力を損ねる可能性が高く、オフライン/社内専用ツールの検討が必要。
- 医療・介護:患者の病歴・治療記録といった要配慮個人情報を扱うため、法令遵守・匿名化・アクセス制限・ローカルLLMの検討など、最も厳格な対応が求められます。
安全な生成AIツールの選び方
「シャドーAI」のリスクを回避しつつ、安心して生成AIを導入するために、ツール選定の際にチェックすべきポイントと主要サービス比較を整理しました。
チェックすべき5つのポイント
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| データ学習ポリシー | 入力データがモデル学習に使われるかどうか、明確に明記されているか。 |
| セキュリティ認証 | SOC 2、ISO 27001などの第三者保証を取得しているか。 |
| データ保存場所と暗号化 | データがどの国・どの地域に保存されるか、通信・保存時に暗号化がなされているか。 |
| アクセス管理機能 | 管理者が利用状況を監視・制御できるか、ユーザー権限を細かく設定できるか。 |
| インシデント対応体制 | セキュリティ事故時の報告体制・補償内容・バックアップ等が整備されているか。 |
主要生成AIサービスのセキュリティ比較(一般論)
| サービス | データ学習 | 主なセキュリティ機能 | 想定用途 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(無料版) | デフォルトで学習に利用可能 | 限定的 | 個人利用、機密情報を含まない一般用途 |
| ChatGPT Team/Enterprise | 学習に利用されない(契約明示) | 管理コンソール・監査ログ | 企業・組織での安全な利用 |
| Microsoft Copilot for Microsoft 365 | Microsoft 365環境内で保護 | Microsoftのセキュリティ・コンプライアンス機能 | Microsoft 365を活用する企業 |
| Google Gemini for Workspace | Google Workspace内保護 | Google Cloudのセキュリティ基盤 | Google Workspaceを活用する企業 |
※実際の契約内容、地域・法令、利用形態によって条件は異なりますので、導入前に必ず個別確認してください。
まとめ:生成AI活用とセキュリティの両立に向けて
本記事では、生成AIによる情報漏洩の仕組み、2025年最新の事例、原因、そして企業が取るべき11の具体的対策について、網羅的に解説しました。生成AIは、もはや無視できないビジネスの変革力を持っています。しかし、その力を最大限に引き出すためには、情報漏洩という重大なリスクに正面から向き合う必要があります。
たとえば、IBM報告が示した通り、AIモデルが侵害された組織の多くがアクセス制御を欠いていたという現実があります。
重要なのは、リスクを恐れて生成AIの利用をためらうことではなく、リスクを正しく理解し、管理可能なレベルにコントロールしながら、その恩恵を享受していくことです。今回紹介した11の対策を参考に、自社の状況に合わせたガイドラインを策定し、従業員一丸となってセキュリティ意識を高めることが、生成AI活用とビジネス成長を両立させるための鍵となります。
特に、機密性の高い情報を扱う企業では、ローカルLLMの導入が最も確実な情報漏洩対策となります。導入に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
生成AI技術とそれに伴う脅威は、今後も日々進化し続けます。一度対策を講じたら終わりではなく、継続的に最新情報を収集し、対策を見直し、改善していくことが不可欠です。本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。