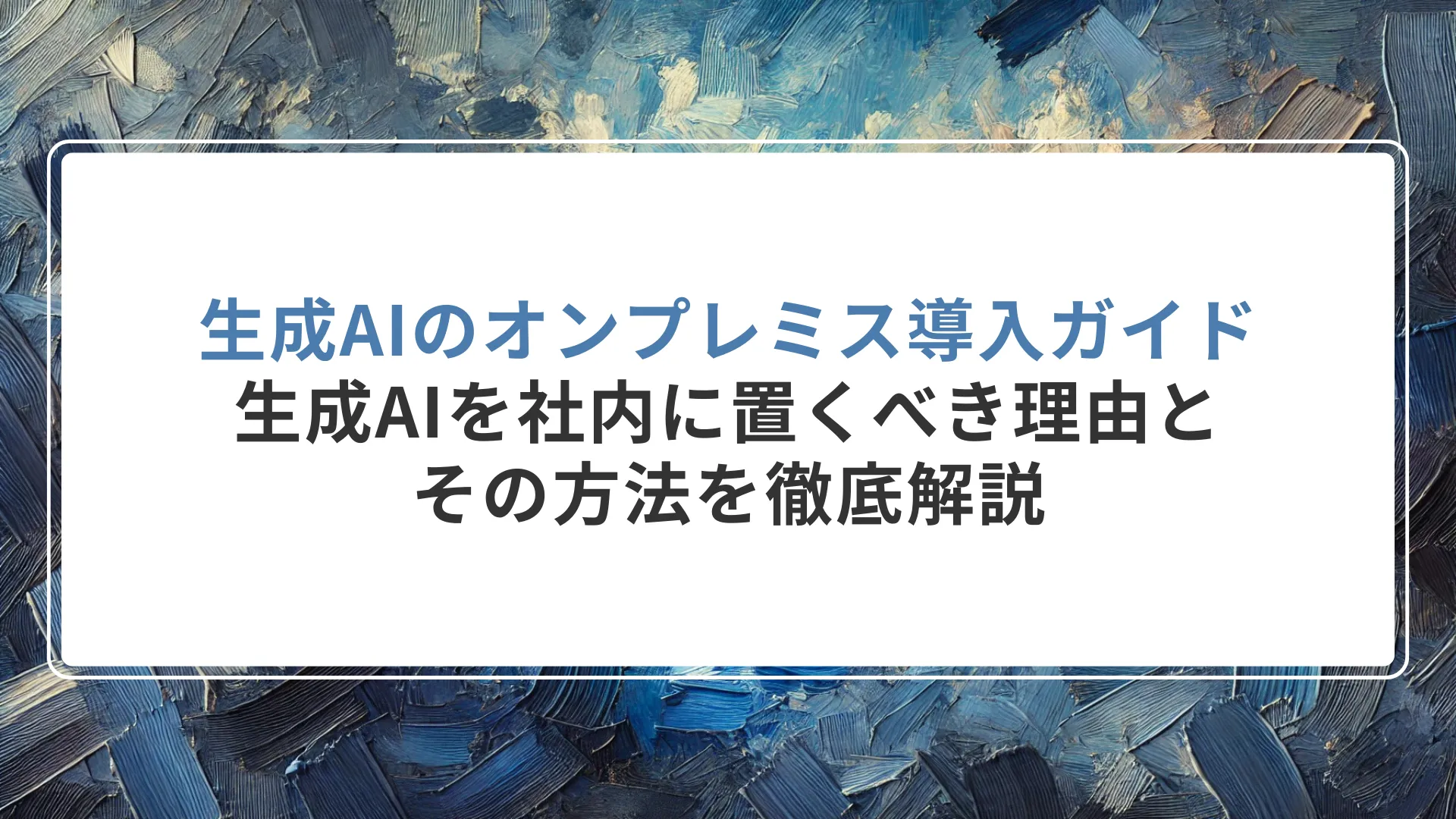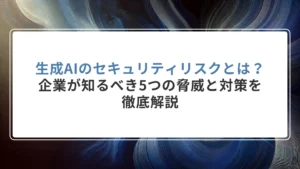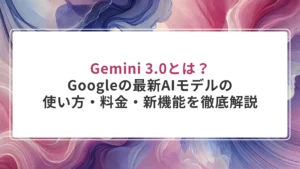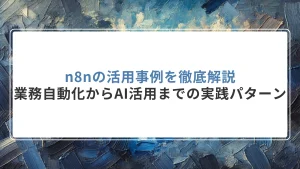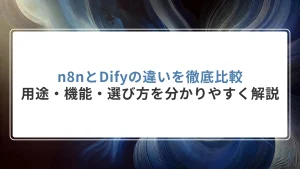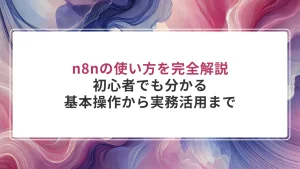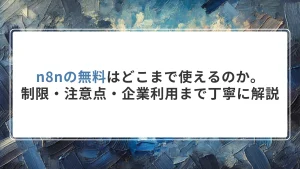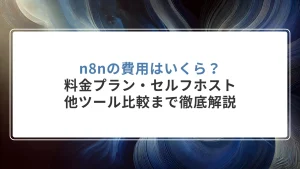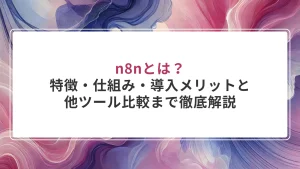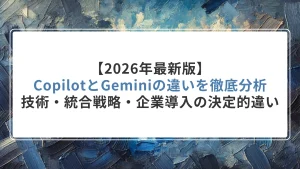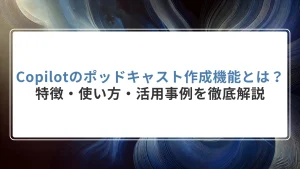「ChatGPTの登場を皮切りに、生成AIはビジネスの世界で“当たり前”の道具になりつつあります。効率化、新たな価値創造…どれも魅力的です。でも、その反面――クラウド依存への懸念もまた、静かに、確実に、企業の中で芽を出しています。
機密情報・個人情報を扱う企業にとって、データを外部に送ることは“もう一つの賭け”です。さらに、従量課金のクラウドでは、「つい使い過ぎてた…」という後悔も現実化しやすい。そんなとき、オンプレミス(自社内で運用するインフラ)は、“選択肢”ではなく“戦略”へと変わっています。
本稿では、オンプレミスで生成AIを始めたいが「何から手をつけたら良い?」という企業のIT担当者・経営者の皆様へ、“全体像”を整理します。メリット・デメリットの比較から、導入ステップ、必要な環境、コスト試算、最新の活用事例まで、MoMoの視点で丁寧に解説します。
生成AIのオンプレミスとは?基本概念と戦略的価値
オンプレミスの基本概念と再評価の背景
「オンプレミス」という言葉自体は目新しくありません。自社施設内にサーバーやソフトウェアを設置・運用する形態を指し、ネットワーク・セキュリティ・ハードウェアすべてを自社で管理する仕組みです。クラウド(外部事業者のリソース利用)とは明確に対を成します。
かつて「クラウド=最適」だった時代もありましたが、生成AIの普及とともに風向きが変わりつつあります。調査では、企業の70〜80%が毎年何らかのデータを「パブリッククラウドから自社環境へ戻している」傾向があると報告されています(いわば“オンプレ回帰”)。
その背景には、“データプライバシー”“コストの予測困難性”といったクラウド利用の課題があるのです。生成AIでは特に、企業が核心とする機密情報・顧客情報を扱う場面が多いため、外部環境を使うことへの抵抗感も大きく、“自社で守る”という選択肢が浮上しています。
生成AIをオンプレミスで導入する戦略的価値
オンプレミスで生成AIを導入することは、防御的なセキュリティ対策というだけではありません。もっと能動的な意味合い――それが「AIソブライニティ(AIにおける主権)」です。自社のAIモデル、データ、運用を自らコントロールするという姿勢です。
この姿勢を手に入れることで、企業は次のような価値を享受できます:
- データ資産の完全な保護:データを自社管理下に置くことで、外部流出リスクを抑えられます。
- 規制・コンプライアンス対応の確実性:GDPRや各業界の厳しい法規制にも、自社ポリシーで確実に対応できます。
- 外部環境への非依存:クラウド事業者のサービス変更、価格改定、事業撤退などのリスクから自社を守り、安定運用が可能です。
こうして、オンプレミスによる生成AI導入は“守り”ではなく“攻め”の戦略にもなるのです。データ×AIを自社の競争優位として活用するための基盤とも言えます。
オンプレミス vs クラウド 徹底比較
生成AI導入にあたっては、オンプレミスとクラウド、どちらが“自社に合っているか”を見極めることが肝心です。どちらが絶対に優れているというわけではなく、目的・用途・規模によって適切な選択は異なります。以下、両者を多角的に比較します。
比較表で見る主な違い
| 項目 | オンプレミス | クラウド |
|---|---|---|
| データ管理 | 自社内で完全制御 | プロバイダーに依存 |
| 初期コスト | 高額(ハードウェア購入など) | 低額(サブスクリプション) |
| 運用コスト | 長期的に低減・安定化 | 利用量に応じて変動・増加 |
| カスタマイズ性 | 高い(自由な構成) | 制限あり(提供範囲内) |
| スケーラビリティ | 物理的制約あり(要計画) | 柔軟(容易に拡張・縮小) |
| セキュリティ | 自社で主導・管理 | プロバイダー基準に依存 |
| 導入スピード | 時間がかかる(構築期間) | 迅速(即日利用可) |
| メンテナンス | 自社で対応(専門人材要) | プロバイダー任せ |
この表を、自社の要件に照らし合わせながら確認すると、「オンプレならでは」の強み・弱みが明確になります。
それぞれに適した企業・ケース
これを踏まて、「どんな企業/利用シーンに向いているか」も整理します。
オンプレミスが適している企業/ケース
- 機密性の高い情報を扱う企業(金融・医療・法務・研究開発など)
- 厳格なコンプライアンス要件がある企業(GDPR、HIPAAなど)
- AIの利用頻度が高く、大規模な処理を行う企業
- 既存システムとの緊密な連携が必要な企業
- AIモデルを自由にカスタマイズしたい企業(オープンソースモデルを利用、自社データでファインチューニングなど)
クラウドが適している企業/ケース
- 迅速にAI導入を始めたいスタートアップ・中小企業
- アクセス数・需要の変動が激しいサービスを提供している企業
- AI運用の専門人材が不足している企業
- 複数のAIサービスを試したい企業
ハイブリッド(オンプレ+クラウド)という選択肢も
実際には、オンプレかクラウドかで迷ったときこそ「ハイブリッドAI基盤」を検討すべきです。例えば、機密性の高い処理をオンプレで行い、モデル学習や急激な需要増えた時だけクラウドを使うという使い分けが考えられます。こうした構成により、両者のメリットを活かし、デメリットを補う設計が可能です。
オンプレミス導入の7つのメリット
オンプレミスには、初期投資や運用負荷という壁がある一方で、「壁を超えた先」にある7つの大きなメリットがあります。
セキュリティとデータ主権の確保
データが社内ネットワークに留まり、外部に送信される機会が極めて少ないため、サイバー攻撃や不正アクセスによる情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。機密性の高い顧客データ、財務データ、研究開発情報を扱う企業にとって、この安心感は計り知れません。
高度なカスタマイズ性
ハードウェアからソフトウェア構成まで自社で自由に設計できるため、例えば「うちの業務プロセスにぴったり合ったAIモデル」「既存システムとの緊密な連携」が可能になります。クラウドでは実現しにくい“自分たちらしさ”を追求できます。
長期的なコスト削減効果
初期投資は確かに大きいですが、AI利用が大規模・継続的なものとなるなら、オンプレミスの方が総所有コスト(TCO)で有利になる可能性があります。従量課金制のクラウドでは、利用量が増えるほどコストも増加しますが、オンプレでは“一度整えたらあとは使い倒す”という構えが取れます。
安定した通信速度とパフォーマンス
社内ネットワーク環境を活用できるため、外部状況に左右されず安定した通信が確保できます。大量データをリアルタイム処理する場面や、遅延が許されないサービス提供には、大きなアドバンテージです。
既存システムとの容易な連携
自社基幹システムや業務データベースとの連携が必要な企業にとって、オンプレ環境は“社内ネットワーク”という強みを活かせます。クラウド導入時に必要なAPI接続やデータ変換・転送の手間が軽減できます。
外部依存リスクの回避
クラウドサービス利用では、提供元の事業者が仕様を変えたり、価格改定を行ったり、最悪サービスを終了したりする可能性もあります。オンプレでは、インフラを自社資産とすることで、こうした“他人任せ”のリスクから自由になれます。
コンプライアンス要件への対応
金融、医療、公共インフラなど、データ取り扱いに厳格な要件がある業界では、オンプレミスが一つの“安心”の選択肢です。物理的な保管場所、アクセス管理、ログ管理、ネットワーク分離――すべて社内でコントロールできるため、法令・ガイドライン対応がより確実になります。
オンプレミス導入の4つのデメリットと対策
もちろん、オンプレミスにはハードルもあります。それを理解し、事前に対策を講じることが、成功への鍵となります。
高額な初期投資
デメリット:高性能GPUサーバー、ネットワーク機器、ストレージ、冷却・電源設備など、インフラ整備に多額の資金が必要です。モデルの規模によっては数千万円の規模になることも。
対策:
- 段階的導入(スモールスタート)でリスクを抑える。
- ワークロードの要件を正確に見積もり、オーバースペックを避ける。
- 国/自治体の補助金制度を活用する。
専門人材の確保
デメリット:GPUやKubernetes、MLOps/LLMOps運用などの専門知識が必要で、それらを持つ人材の採用・育成は簡単ではありません。
対策:
- 社内人材のアップスキリング/研修による育成。
- 外部ベンダーやコンサルティング企業との協業。
- 統合プラットフォーム導入で管理の難易度を下げる。
運用の複雑性
デメリット:ハードウェアの物理管理から、ソフトウェア更新、障害対応、モデル管理まで、運用負荷が高くなります。
対策:
- MLOps/LLMOpsを導入し、運用サイクルを自動化・標準化。
- インフラ構成管理や監視を自動化するツール(例:Ansible、Prometheus)を活用。
スケーラビリティの制約
デメリット:クラウドの“ワンクリックで拡張”とは異なり、物理ハードウェアを追加・設置する手間が必要です。急な需要増には対応が遅れる可能性があります。
対策:
- 将来の需要を見越して計画的に設計。
- モジュラー設計で、必要な機能だけをスケールアウト可能にする。
- 通常はオンプレで対応し、突発的な負荷にはクラウドを併用するハイブリッド構成を検討。
どんな企業がオンプレミスを選ぶべきか
「うちには合っているか?」という問いに答えるため、業界別・企業規模別に、オンプレミスが適しているケースを整理します。
業界別の適性
特に以下の業界では、データの機密性・規制の観点からオンプレミス導入が“合理的な選択”となります。
- 金融業界:顧客の資産情報・取引履歴などを扱うため、厳格な安全対策基準があります。
- 医療・ヘルスケア:患者カルテ・ゲノム情報など、プライバシー極めて高いデータを扱います。
- 製造業:製品設計データ・製造ノウハウ・サプライチェーン情報を競争優位の源泉とする企業が多く、“外部流出を断つ”ためにオンプレを選ぶことが増えています。
- 公共機関・重要インフラ:国民の個人情報・社会インフラ制御情報などを扱うため、外部依存を極力排した設計が求められます。
企業規模・利用規模による判断基準
- 大企業:既に多くの社内システムを保有し、AIを全社的に大規模活用する計画がある場合、オンプレミスが適しています。膨大なデータ処理、専任IT部門の存在という点で強みがあります。
- 中堅企業:特定部門でのAI活用、明確なROIが見込めるユースケースなら、オンプレミスが有効です。ただし、初期投資・人材確保というハードルは注意が必要です。
- スタートアップ・小規模企業:一般的にはクラウドが有利ですが、独自アルゴリズム開発・知的財産管理が事業の核となる場合には例外的にオンプレミスが検討対象となります。
最終的には、「自社の扱うデータの機密性」「AIの利用規模と頻度」「コンプライアンスの厳しさ」「長期的なコストとROI」を総合的に評価し、自社戦略に最も合った選択をすることが重要です。
オンプレミス導入に必要な環境・要件
オンプレミスで生成AIを運用するには、ハードウェア・ソフトウェア・人材の3要素が揃っていることが前提です。それぞれについて具体的に掘り下げます。
ハードウェア要件
生成AI(特に大規模言語モデル=LLM)の運用には、一般的なWebサーバーでは足りません。以下は主な要件です。
- GPU/AIアクセラレータ:並列処理を高速に行うために必須。例として、NVIDIA A100/H100、推論専用のL40、比較的小規模ならRTX 40シリーズなど。
- サーバー・システム仕様:モデル規模により必要仕様が異なります。例えば:
- 小規模モデル(~13B):RTX 4060/4070、12GB VRAM、32GB RAM、NVMe SSD
- 中規模モデル(~70B):RTX 4090/A100、24‑40GB VRAM、64GB+ RAM、NVMe SSD
- 大規模モデル(70B~):A100/H100 複数、80GB+ VRAM、128GB+ RAM、分散 NVMe ストレージ
- ネットワーキング・インフラ:複数GPUサーバーで高速通信が必要。10Gbps以上、より高性能なら25Gbps以上が推奨。
- 冷却・電源設備:高性能GPUは多くの熱を発します。適切な空調・電源設備がなければ、稼働安定性が確保できません。
ソフトウェアスタック
ハードだけでなく、ソフトウェアも“生成AIならでは”の構成が必要です。
- 推論エンジン/サーバー:学習済みモデルを効率良く動かすためのソフト。「NVIDIA Triton Inference Server」「vLLM」などが代表的です。複数リクエストのバッチ処理等も可能になります。
- コンテナ化・オーケストレーション:「Docker」でアプリをパッケージ化、「Kubernetes」で多数のコンテナを自動管理するのが主流。
- MLOps/LLMOpsプラットフォーム:モデル管理・実験追跡・デプロイ自動化などを支援。「MLflow」「Kubeflow」などがオープンソースで利用できます。
- ベクトルデータベース(RAG用途):文書をベクトル化して格納・検索するための技術。「Milvus」「Weaviate」などが代表的です。
人材・体制
これらのインフラ・ソフトを“使いこなす”には、次のような人材・チーム構成が求められます。
- AI/MLエンジニア:モデル選定、ファインチューニング、性能評価などを担当。
- インフラエンジニア:GPUサーバー構築、ネットワーク設定、Kubernetes運用などを担当。
- データサイエンティスト:ビジネス課題を分析し、どのデータを学習させるか、どのように活用するかを設計。
- セキュリティ専門家:AI基盤全体のセキュリティポリシー策定・実装・監査を担当。
すべてを社内で揃えるのが難しい場合は、外部の専門ベンダーと協業することで「人・モノ・仕組み」を補完する戦略も有効です。
利用可能な生成AIモデル(2025年11月時点)
オンプレミス対応可能な生成AIモデル、特にオープンソース/日本語特化型を中心に紹介します。
主要なオープンソースLLM
世界中で研究・開発が進んでいるオープンソースLLMは、オンプレミス導入の強力な選択肢です。商用利用可能なものも増えています。例えば:
- Llama 3.1(Meta): 8B、70B、405Bといったモデルサイズがあり、高性能な代表格。7億MAU超のサービスではライセンス申請が必要なケースも。
- Mistral(Mistral AI): 7B、8×22Bモデルがあり、軽量・効率的な設計。Apache 2.0ライセンスで提供。
- Gemma 2(Google): 9B、27Bのモデル体系。Google開発。
- Qwen 2.5(Alibaba): 0.5B~72Bまで幅広く、マルチ言語対応に優れ、Apache 2.0ベース。
日本語特化LLM
日本語処理・文化的文脈の理解を重視するなら、国内モデルも要チェックです。例えば:
- ELYZA‑japanese‑Llama‑2‑7b:東京大学松尾研究室発のスタートアップ ELYZAが開発。商用利用可能で、日本語の対話能力に定評あり。
- RakutenAI‑7B‑Instruct:楽天グループが公開。日本語データで高品質学習されており、自然な応答が特徴。Apache 2.0ライセンス。
- Swallow LLM系列:東京工業大学と産業技術総合研究所による共同開発。学術用途中心だが、日本語性能が高い。
- 商用日本語LLMとして、tsuzumi(NTT)やcotomi(NEC)なども。オンプレ対応、高性能だがライセンス費用が必要。
ライセンスの注意点
オープンソースモデルであっても、ライセンスを“ちゃんと読む”ことが極めて重要です。
例として:
- モデルが「Apache 2.0」など比較的緩やかなライセンスで公開されていても、商用利用・大規模サービス化にあたっての別途契約が必要な場合あり。
- Meta社のLlamaシリーズなど、サービスの月間アクティブユーザー数(MAU)に応じてライセンス申請が必要なケースがあります。
- 法務部門と連携し、「モデルの出力をどう使うか」「データをどのように学習に使うか」「顧客にどう提供するか」という観点から契約条件を整理しましょう。
導入ステップと注意点
オンプレミス生成AI導入は、一足飛びには成功しません。計画的なステップを踏むことが、モモ株式会社としても強くお勧めするアプローチです。
段階的な導入アプローチ
以下の5つのステップで進めると、リスクを抑えながら着実に基盤を築けます:
- ユースケースの明確化とROI試算:何のためにAIを使うのか、どの業務に適用するのかを定義し、導入によるコスト削減・売上向上の効果を試算。経営層へ合意取得。
- パイロットプロジェクト(PoC)実施:特定部門・ユースケースに絞った小規模実証を行い、技術・効果・運用可能性を確認。
- 環境構築:ハードウェア調達、インフラ構築、ソフトウェアスタック導入。将来の拡張性も視野に設計。
- モデル選定・導入およびカスタマイズ:ユースケースに最適なモデルを選び、自社データでファインチューニング・カスタマイズ。
- 本格運用と評価・改善:業務適用を開始し、ユーザーフィードバック・性能データを収集。定期的に評価し、再学習・改善のサイクルを回す(MLOps/LLMOps)。
導入時の注意点
- セキュリティ対策の徹底:オンプレは「安全」とされがちですが、適切な対策なしではただの“閉じた箱”になってしまいます。ネットワーク分離、アクセス制御、暗号化、脆弱性診断などを多層的に。
- データガバナンスの確立:学習データ・生成された情報の取り扱いルールを策定。個人情報・機密情報の不適切利用を防ぐ体制が必要です。
- 法規制・倫理への配慮:データ利用に関する法令(例:個人情報保護法)、AIの倫理(偏り・差別・誤情報)に対応。社内ガイドライン・従業員研修を行うと安心です。
業界別導入事例
“言われている”だけでなく、“実際に導入されている”という事実から学びましょう。業界別の参考事例をいくつか紹介します。
金融業界
- 三菱UFJ銀行:金融専門用語を学習させた生成AIをオンプレ環境で導入。文書作成・翻訳・要約などで、月間最大22 万時間の業務時間削減効果を試算しています。
- あおぞら銀行: neoAI社と協力し、オンプレ型次世代AI基盤を構築。金融業務特化のLLM「“あおぞらLLM”」を開発・運用。応答精度向上・行員の業務効率化などを目指しています。
製造業
- 本田技研工業:熟練技術者のノウハウが詰まった大量の技術文書(画像・グラフ多)から、データ資産を抽出・構造化するためにLLMを活用。オンプレ環境で機密性を確保しつつ、次世代車両開発を加速させています。
- Siemens(アンベルク工場):産業用PCを活用したオンプレAIソリューションを導入。生産ラインの品質管理・予知保全に生成AIを適用し、品質逸脱42%削減・設備総合効率(OEE)37%向上という結果を報告しています。
医療・ヘルスケア
- 横須賀共済病院・亀田総合病院:TXP Medical社提供の、オンプレ環境で動作する生成AI医療文書作成システムを導入。医師の会話を録音するだけで、AIが電子カルテの下書きを作成。機密性の高い医療情報を院外に出さず、医師の事務作業負担を大幅に軽減しています。
これらの事例から見えてくるのは、各業界が「業務効率化」「ノウハウ継承」「セキュリティ確保」という課題を背景に、オンプレミスという“選択肢”を戦略的に採用しているということです。
コスト試算と損益分岐点
オンプレミス導入を判断する際、コストは避けて通れないテーマです。ここでは、初期投資の目安とクラウドとの損益分岐点について整理します。
初期投資の目安
モデル規模・性能仕様によって大きく変わるため、目安として以下を参考にしてください:
- 小規模導入(PoC/特定業務向け):50万円〜300万円。7B〜13Bクラスのモデル1台稼働を想定。
- 中規模導入(部門・複数業務向け):300万円〜1,500万円。70Bクラスモデル稼働、複数並行利用あり。
- 大規模導入(全社基盤):1,500万円〜数億円。複数の大規模モデルを常時稼働、学習・ファインチューニングも実施。
クラウドとのコスト比較と損益分岐点
クラウドのAPIサービスは“始めやすい”反面、利用量が増えるとコストが増大します。オンプレミスは初期が重いですが、長期的には違いが出ます。
- 損益分岐点の目安としてある調査では、中規模の推論ワークロードなら2〜3年程度でオンプレミスのTCOがクラウドを下回るとしています。大規模・24時間365日稼働のケースでは1年未満という報告もあります。
- TCO(総所有コスト)を比較する際には、初期投資だけでなく、運用人件費、電気代、保守費用、ライセンス料、クラウドの場合ならデータ転送料/ストレージ費用なども含めて考えることが重要です。
自社のユースケースに沿って、複数のベンダー見積もりを取得し、具体的にシミュレーションしておくことが賢明です。
まとめ:データ主権を握り、戦略的AI活用を実現するオンプレミス
これまで、生成AIのオンプレミス導入について、基本概念からメリット・デメリット、導入方法、コスト、最新事例まで、MoMo視点で整理しました。
クラウドAIが“手軽さ・柔軟性”で普及している一方で、セキュリティ、カスタマイズ性、データ主権という観点から、オンプレミスは多くの企業にとって戦略的に強い選択肢となりつつあります。特に、機密情報を扱う企業やAIを大規模に活用する企業にとって、その重要性はこれからさらに高まっていくと考えています。
オンプレミス導入には確かにハードル(初期投資・専門人材・運用負荷)がありますが、段階的な取り組み、外部パートナーとの協業を通じて、十分に乗り越え可能です。
成功の鍵は、明確な目的意識を持ち、自社に合った設計・運用を計画的に進めること。そして何より「データという企業の最も重要な資産を自らコントロールする」という姿勢を持つことです。
オンプレミス生成AI導入のために、MoMoとしてお勧めしたい重要ポイント
- 明確なユースケース定義とROI試算を行う
- スモールスタートから段階的に導入を進める
- 自社の要件に合ったハードウェア・ソフトウェアを選定する
- セキュリティとデータガバナンス体制を確立する
- 継続的な評価・改善サイクルを構築する
生成AIの活用は、もはや「業務効率化のツール」ではなく、企業の競争優位性を左右する“経営課題”です。この記事が、貴社にとって「最適なAI戦略」を描き、データという最も大切な資産を自社のコントロール下に置きながら、持続的な成長を実現する一助となれば、MoMoとして大変嬉しく思います。
まずは、自社のどの業務を“生成AIに任せられるか”、小さなPoCからでも検討を始めてみてはいかがでしょうか?