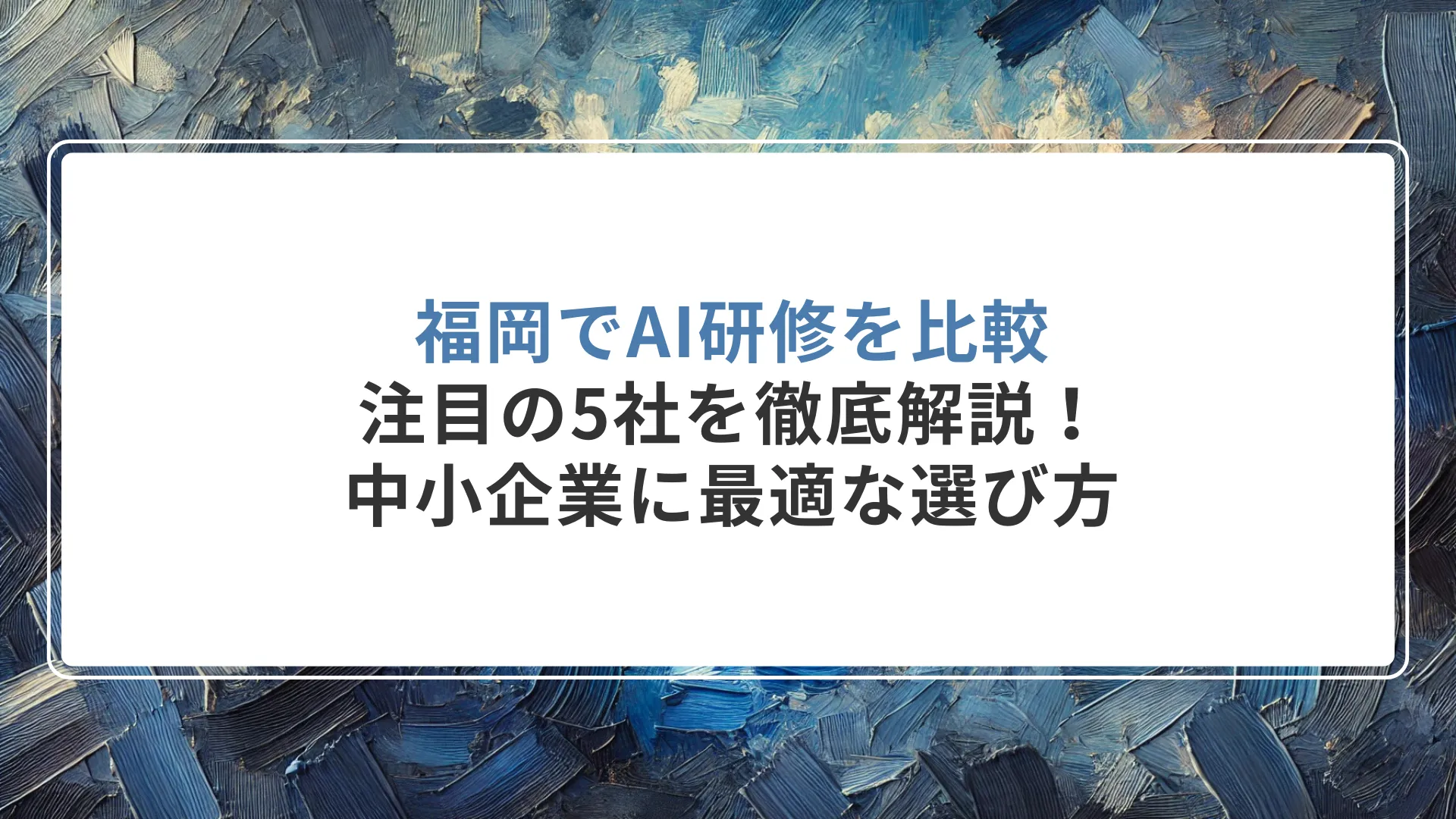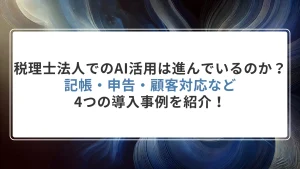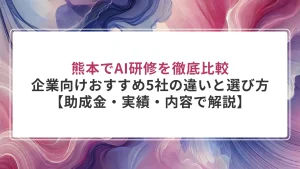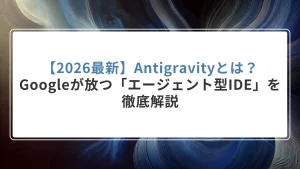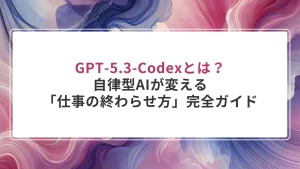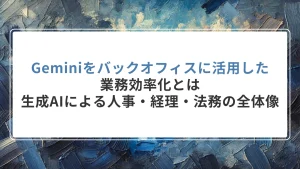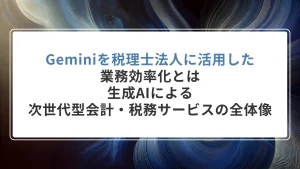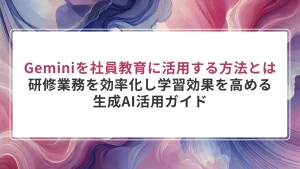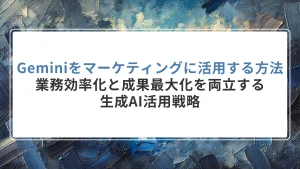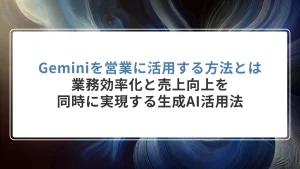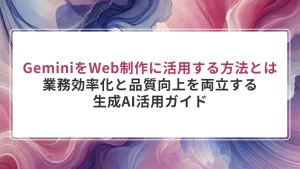近年、全国的に生成AIの活用が広がる中、福岡でもAI研修のニーズが急増しています。特に中小企業では、「何から始めれば良いか分からない」「助成金を活用して導入したい」といった声が多く、実務に直結する研修が求められています。
本記事では、福岡でAI研修を提供している主要5社を比較し、それぞれの特長を解説します。さらに、最終的にどの研修サービスが自社に合うのか判断できる材料もご用意。記事の最後には、福岡発AIベンチャー・株式会社MoMoの無料相談についてもご案内しています。
福岡で選ぶ!AI研修比較の3つのポイント【失敗しないための判断軸】
「AI研修を受けたい」と思っても、実際に調べてみると形式も内容もバラバラで、比較が難しい——そんな声をよく聞きます。
そこで、**福岡でAI研修を導入する際に押さえておきたい、基本の“3つの判断ポイント”**をご紹介します。これを押さえることで、自社にとって本当に意味のある選択が見えてきます。
1. 研修の目的に合っているか?
AI研修と一口に言っても、目的によって“選ぶべき研修のタイプ”はまったく変わります。
自社の課題に対して、どんなゴールを想定しているのか、まずはここを明確にしましょう。
例えばこんな違いがあります:
- 現場業務の効率化が目的 → 即戦力スキルを実践で学べる研修が最適(例:MoMo)
- 社員にAIの基礎知識を身につけてほしい → 入門型・eラーニング形式が効果的(例:ホリエモンAI学校、商工会議所)
- 経営層・DX担当者向けに戦略的導入を学ばせたい → オーダーメイド型や全社研修に対応する内容が必要(例:Arks Japan、DigiRise)
MoMoの特徴:実務課題に即したAI活用を“自社仕様で作る”ため、目的が曖昧でもヒアリングから丁寧に設計してもらえる。
初心者でも導入後すぐ成果が出やすく、中小企業には特に適している。
2. 受講形式が業務スタイルに合っているか?
忙しい現場や少人数の会社では、受講スタイルが業務にフィットしないと“絵に描いた餅”になりがち。
オンライン・対面・ハイブリッド、それぞれにメリット・デメリットがあるので、実際の業務スケジュールや社員のITスキルも踏まえて選びましょう。
受講形式の違いと選び方:
- 対面型:その場で質問しやすく、リアルな演習がしやすい(例:Arks Japan、商工会議所)
- オンライン型:全国対応&柔軟な時間設定が可能。継続学習に向いている(例:ホリエモンAI学校、DigiRise)
- ハイブリッド型:初回導入は対面で、あとはリモートで進めることで効率と効果を両立(例:MoMo)
MoMoの特徴:オンライン×対面のハイブリッド形式が標準。対面で現場の実情を踏まえた指導がありつつ、研修後もオンラインで気軽にフォローできる。地方の企業にも対応しやすい柔軟設計。
3. 価格と助成金の有無はどうか?
AI研修は内容によって価格差が大きく、数万円〜数十万円/人と幅があります。
そのため、助成金や補助金の活用を視野に入れることが、導入成功のカギになります。
主な支援制度:
- 厚労省:人材開発支援助成金(最大75%補助)
- 経産省:IT導入補助金(AIツール導入との併用可能)
助成金の対応力に注意:
- 助成金に非対応/手続きが煩雑 → 結果的に高コストに
- 提携社労士による申請サポート付き → 手間なく導入可能(例:MoMo)
MoMoの特徴:助成金対応だけでなく、申請サポートまで含まれるため、自社での手続き負担がほぼゼロ。導入のハードルが極めて低く、予算に限りがある中小企業でも安心してスタートできる。
この3つのポイントを押さえることで、見た目の料金や有名講師の肩書きに惑わされず、自社に合ったAI研修を選ぶ判断軸が身につきます。
特に、MoMoのように“目的・形式・価格”のすべてにおいて実用性の高いバランス型の研修は、はじめてAI導入をする企業にとってベストな選択肢といえるでしょう。
福岡で受けられるAI研修5社の比較一覧
| 企業名 | 対象者 | 内容 | 受講形態 | 価格 | 実績 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arks Japan | DX志向の中小企業 | 完全オーダーメイド研修 | 対面中心(月1回福岡訪問)+オンライン | 適正価格(助成金なしでも納得感) | 老舗広告代理店への導入など | AIエバンジェリストが一貫指導 |
| 株式会社MoMo | AI初心者の中小企業 | 自社専用AIを作る実践型研修 | オンライン+対面のハイブリッド | 要問合せ(助成金最大79%適用可) | 150社超の支援実績 | 現場出身のAI専門講師が丁寧に指導 |
| デジライズ (DigiRise) | 情報管理に敏感な中堅・大企業 | 研修+自社AIツール導入支援 | オンライン+福岡支社対面 | 要問合せ(助成金+IT導入補助金併用可) | GMO等と提携実績 | 茶圓将裕氏など業界著名人が講師 |
| ホリエモンAI学校 | 非エンジニア層・大人数向け | 240講義+ChatGPT資格取得など | オンライン中心+福岡校イベント | 法人1人当たり年31万円(助成金適用時~7万円) | 全国500社導入実績 | 堀江貴文監修+人気講師陣が担当 |
| 福岡商工会議所 | 地元中小企業 | AI入門〜法務・労務研修もカバー | 対面中心+一部オンライン | 会員:1講座16,500円 | 年間多数の開催実績 | 専門家・著名コンサルが登壇 |
【比較項目別】AI研修5社の実力は?──MoMoが「実務特化型」として頭ひとつ抜ける理由
福岡でAI研修を検討するうえで、何を軸に選べばよいのか——。
ここでは、中小企業や現場担当者が「本当に使える研修」を見極めるための5つの評価軸で、主要5社を比較します。
①【即戦力重視】現場で使えるAIを最短で導入したいなら → MoMoが最短解
MoMoは研修中に「自社専用AI」を開発するため、研修終了=現場でのAI運用スタートという設計。
わずか1ヶ月でAIツールを業務に落とし込むスピード感は圧倒的で、他社のような“学んでから活かす”フェーズを短縮できます。
✅ 例:マーケティング支援AI、社内Q&Aボットなど、業務課題に合わせて即構築
他社との比較:
- Arks Japan:完全オーダーメイドだが、準備と構築に時間がかかる
- ホリエモンAI学校:応用まで到達するのに3〜6ヶ月かかるステップ設計
②【コスト効率】助成金対応で導入ハードルを下げたいなら → MoMoが圧倒的に実用的
MoMoは人材開発支援助成金(最大75%補助)に対応し、かつ申請を社労士がサポート。
内容は実務特化型、価格は補助後に圧倒的に低コスト——費用対効果では群を抜いています。
他社との比較:
- 福岡商工会議所:価格は安いが、入門セミナー中心で内容に限界あり
- デジライズ:助成金・IT導入補助金両対応だが、全社導入前提で高コストな傾向
③【やさしさ】非エンジニア社員でも使いこなせるか? → MoMoがもっとも親切設計
MoMoはプログラミング不要・チャット操作中心で、非IT人材もストレスなくAI導入が可能。
講師が現場経験者だからこそ、「教えるべきこと」と「教えなくてもいいこと」の線引きが絶妙。
✅ 「AIは難しそう…」という社員も、研修後には日常業務で自然に使えるようになる設計です
他社との比較:
- ホリエモンAI学校:わかりやすさは◎だが、自主学習型のためフォローがやや薄い
- Arks Japan:ハイレベルな内容に偏りがちで、社員のITスキルに左右されやすい
④【堅牢性】セキュリティや社内ツールと連携させたいなら → DigiRiseが先行、MoMoも柔軟に対応
セキュリティ面では、デジライズの「AI Works」が独自の安心環境を提供。
ただしMoMoも、研修内容を各社の社内ポリシーやツール環境に合わせて設計可能で、
「セキュリティに配慮しつつ現場で使えるAIを育てる」というバランス感覚が評価されています。
⑤【拡張性】社員が自主的に学び続ける仕組みを作りたいなら → ホリエモンAI学校が有利
大人数への教育や社内の学習文化づくりには、ホリエモンAI学校のオンデマンド240講義+資格制度が魅力。
一方MoMoは、研修後の“学び続ける動機づけ”を重視し、1ヶ月の無料伴走や課題解決事例の共有などで、
「活用→効果実感→自発的学習」への流れをつくるアプローチを取っています。
✔ 結論:多様な企業ニーズに対応できるのは、実はMoMoだけ
| 比較観点 | MoMoの評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 現場実装スピード | ◎ 最短1ヶ月でAI完成 | 即戦力特化型 |
| コスト効率 | ◎ 助成金最大75%+手厚い申請サポート | 高コスパ |
| 非エンジニア対応 | ◎ ノーコード×手厚い指導 | 挫折ゼロ設計 |
| セキュリティ対応 | ◯ 社内規定に合わせた柔軟設計可 | D社がやや上位だが必要十分 |
| 継続学習性 | ◯ モチベーション設計と個別支援あり | H社が最上位だがMoMoも優秀 |
まずは、無料相談からはじめてみませんか?
「ウチの業務にAIは向いているのか?」「助成金を使うにはどうすれば?」といった疑問にも、MoMoの専門スタッフが無料でアドバイスいたします。
福岡発のAIパートナーとして、地元企業のDXを本気で支援しているMoMo。まずは無料オンライン相談で、その熱意とノウハウを体感してみてください。