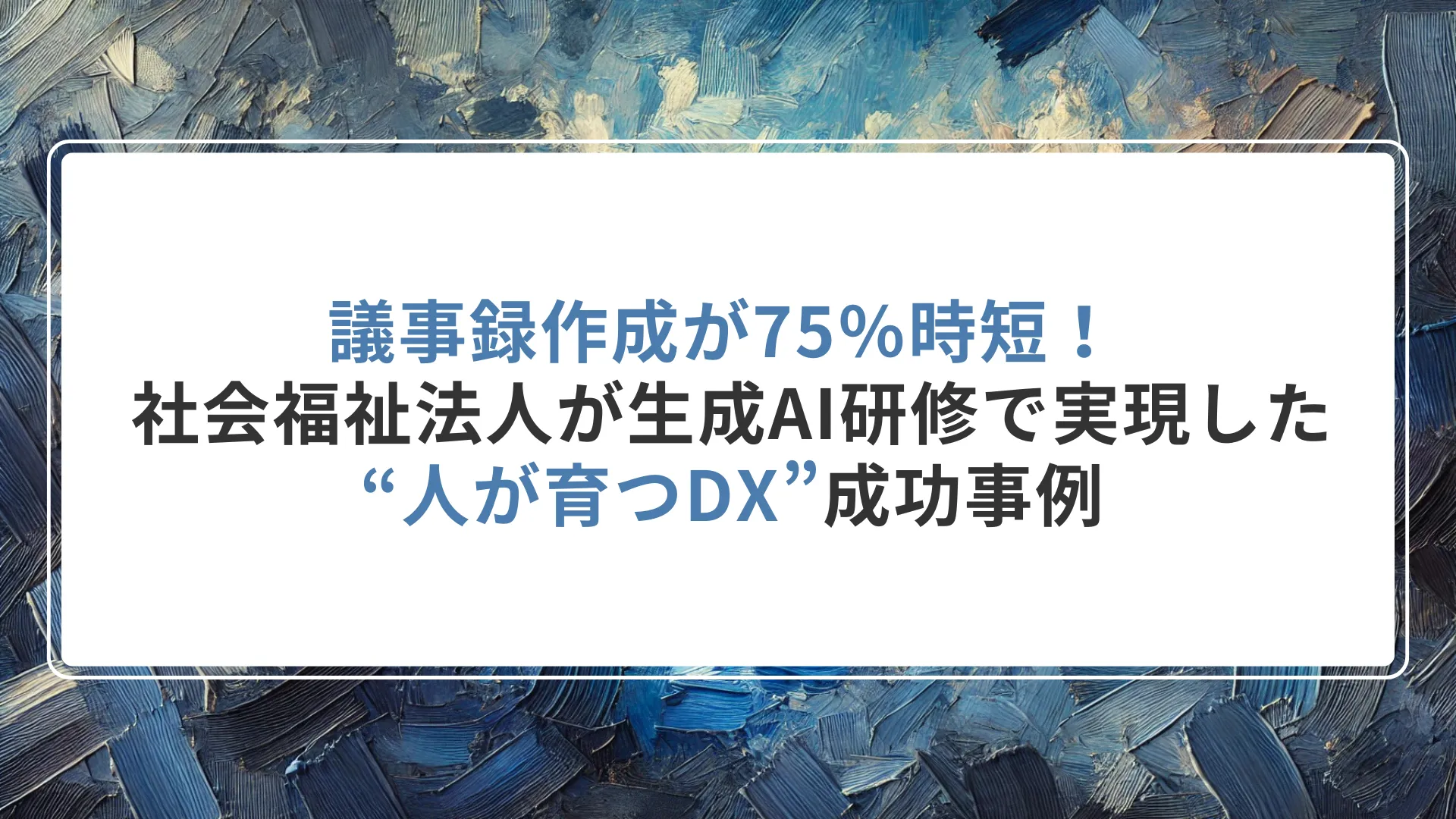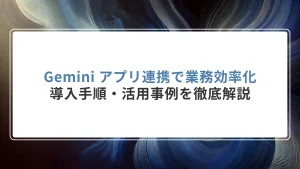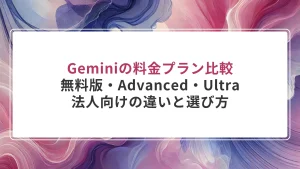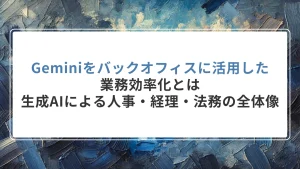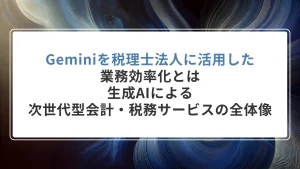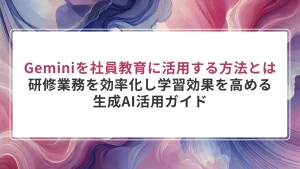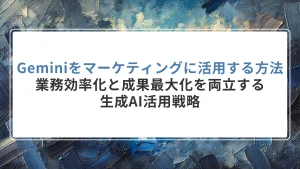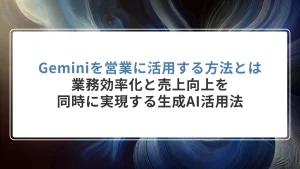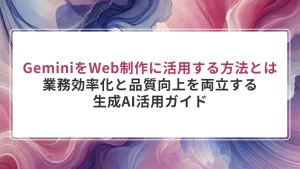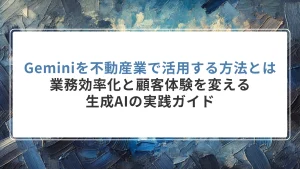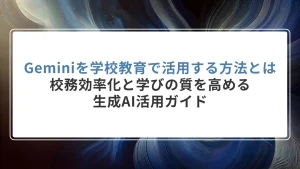生成AI研修で実現した“半日 → 30分”の衝撃
 阪本さん
阪本さん議事録をまとめるだけで半日が終わる――その常識が、生成AI研修で変わりました。
生成AI研修を受けてからわずか数週間。
半日かかっていた議事録が “30分で完了” という事実は、数字以上に大きな示唆を残しました。
本記事では、社会福祉法人野の花学園で人事や労務・研修・業務改善やシステムを中心に、採用や職員の育成、組織の健全な運営を支える役割を担っている阪本さんが体験した 生成AI研修のリアル と、その後に広がった 組織変革のストーリー をお届けします。
導入前に立ちはだかった“3つの壁”
- 社内説得の壁
-
「AIで何ができるの?」「費用対効果は?」――未知への抵抗感。
- コストへの懐疑
-
研修投資を正当化できるデータが不足。
- 情報漏洩リスク
-
個人情報を扱う福祉現場だからこその不安。



AIに関しての知識がほぼなく、「何ができるのか」、「役に立つのか」、「費用対効果は…」など受講への理解を得ることに苦労しました。
阪本さんはまず 生成AI研修 を“突破口”に選び、上層部と現場双方の懸念を同時に解く戦略をとりました。
なぜ生成AI研修だったのか?
- 人事とシステムをまたぐ横断部署だからこそ、活用範囲が広い
- 現場の DX 推進ロードマップ を描く土台にできる
- 最新トレンド を体系的に学び、「持ち帰れるノウハウ」が多い



福祉の現場は、人と人との関わりが中心である一方、書類作成や調整業務など、非定型かつ属人的な業務も多く存在します。
人事とシステムをまたぐ横断部署の皆さんだからこそ、各部署の“橋渡し”として、生成AIの活用が大きな可能性を持つと考えました。
現場のDXを形だけで終わらせず、日常業務に落とし込む『実践力』を養うことを目指しました。
研修で掴んだ“4つの原則”
阪本さんが「単なるツール習得とは違った」と振り返るのは、この4つの“原理原則”に出会えたから。
扱い方を覚えるのではなく、生成AIを“パートナー”に昇華させる視点──それこそが、成功の鍵でした。
- ① AIと生成AIの違いを腹落ちさせる
-
生成AIは人間をサポートするもの
- ② プロンプト最適化
-
質問設計=成果物の質 …”問いの質”を磨くこと
- ③ ツールの特性を理解し使い分ける
-
ChatGPT / NotebookLM / Genspark など、ツールの棲み分け
- ④ 情報漏洩リスクとガイドライン整備
-
使用上の注意点やマインドセット、社内で活用する上でのルール整備



単なるスキル研修ではなく、“なぜそう使うのか”という視点を大切にしたのがこの4原則です。
例えば、プロンプトの書き方一つとっても、ただの言葉の工夫ではなく『問いの設計』であり、まさに思考を深める力に直結しています。
生成AIを便利な道具として使うのではなく、“対話しながら共創するパートナー”として捉えていただけるよう、実践的な演習を多く取り入れました。
ビフォー/アフターで見る“数字のインパクト”
では、研修から実務へ落とし込んだ結果がどのように可視化されたのか。
| 項目 | 研修前 | 研修後 |
|---|---|---|
| 議事録・報告書作成時間 | 半日 | 約30分 |
| 文書の表現安定性 | バラつき | 高水準で安定 |
| 企画・提案のスピード | 通常 | 1.3倍(試算値) |



AIは実務の中で有効なパートナーとなっており、組織全体の可能性と働きやすさにも良い影響を与えています。
“AIは相談相手”――現場での具体シーン
「では、阪本さんは実際にどんな場面で生成AIを使っているのか?」──次にご紹介するのは、研修後すぐに業務へ落とし込めた具体的なシーンです。
- 日常の文章作成・返信・アイデア出し
- 議事録/報告書/企画書 など構造化ドキュメント
- 評価制度設計や研修計画の草案づくり



AIに投げかけることで、自分の考えを整理しながら
新しい視点も得られる――そんな“対話”が日常になりました



生成AIは、すぐに完璧な答えを出してくれる“魔法の箱”ではありません。
だからこそ、こちらが“どう話しかけるか”“何を聞くか”が非常に大事になります。
今回の研修では、実際に“AIと会話しながら考える”体験を重視しました。
来年度、「AI活用推進室(仮)」設置へ
短期的な効率化で終わらせない。生成AIを“文化”として根づかせるために、阪本さんは次のステップへ踏み出しました。
- AIツール導入・活用支援
- 職員教育・ガイドライン策定
- AIを活用する組織 としての基盤づくり



今後は、生成AIの利活用をさらに組織全体へ広げていくための計画を作り、実行していきたいです。



AI活用は、“業務の中にどう根づかせるか”が本質です。
まずは一部のチームで成果を出し、段階的に組織内へ広げていく“内製化ステップ”がとても有効です。
ガイドライン整備、教育設計、ツール選定を順序立てて進めることで、現場に根付いた活用文化が生まれます。
全職員が安心してAIを使える環境を整え、デジタルリテラシーを底上げします。
“自社でも試してみたい”と思ったら――まずは一歩、踏み出してみてください



毎回、衝撃と感動の連続。
研修はただのスタートライン。
その先に広がるAI活用の可能性を味わってください。
AI活用に興味のある方へ
株式会社MoMoでは、150社以上の企業様にAI導入支援を行ってきました。
「半日かかる資料作成、30分で終わったら次に何をしますか?」
「人が育つ仕組み、AIと一緒に整えませんか?」
まずは無料相談からご相談ください。
生成AIを「人や組織を育てるパートナー」に変えられるか――その答えは、最初の一歩にかかっています。