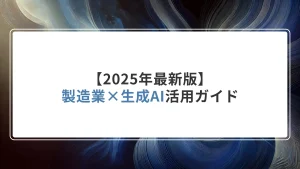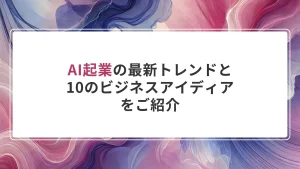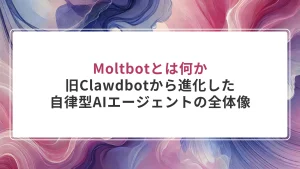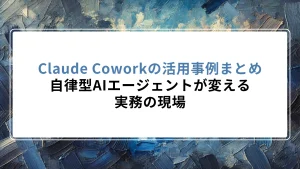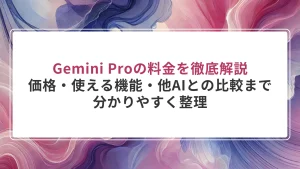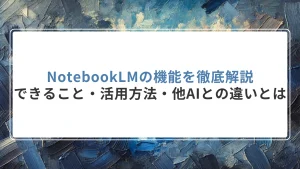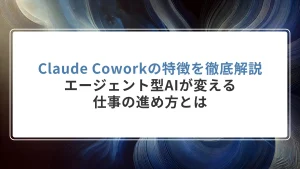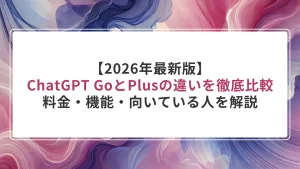―導入担当者のための作成手順とチェックポイント―
ChatGPTを社内導入する際に欠かせない「社内規定ガイドライン」の作り方を5ステップで解説します。
個人情報保護法・経産省AIガイドラインなど最新法規対応、入力禁止データ例、教育・運用ルールまで具体例付きで網羅します。
なぜChatGPT利用時のガイドラインが不可欠なのか
機密情報流出リスク
Samsung 技術者が ChatGPT に社内コードを貼り付けてしまい、外部サーバに漏えいした事例が発生。社内統制なしでは同様の事故が再発する可能性があります。
生成AIを「すでに業務で利用」する国内企業は45.0%、一方で「利用を従業員判断に任せている」企業が14.4%あり、組織的統制の欠如が浮き彫りになっています。ガイドライン策定率はまだ19.5%にとどまります。
出典:MALWARENEWS
個人情報・プライバシー法令違反
個人情報保護委員会はChatGPTを含む生成AI利用に対し「機密情報や個人データの入力禁止」「誤情報リスクへの対策」を注意喚起しています。
出典:個人情報保護委員会
国内ガイドライン適合
経産省のAI事業者ガイドライン Ver 1.1(2025/3/28)は、開発・提供だけでなく利用企業もリスク評価と運用プロセスの整備を求めています。
出典:経済産業省
ChatGPT社内規定ガイドライン策定 7ステップ
| ステップ | 目的 | 具体アウトプット(例) |
|---|---|---|
| 1. 組織体制の確立 | 責任と承認フローを明示 | 「AIガバナンス委員会」規程/RACI表 |
| 2. 利用目的・範囲定義 | “実験⇨本番”移行条件を設定 | ユースケース・リスクマトリクス |
| 3. データ分類と取扱い | 入力禁止データを確定 | レベル別入力禁止リスト |
| 4. セキュリティ・権限制御 | 技術的ガードレール | SSO/VPN/内部LLMプロキシ設計書 |
| 5. 出力品質・検証 | ハルシネーション抑止 | 二重レビュー+RAGチェックシート |
| 6. 法令・契約遵守 | 国内外規制を網羅 | コンプライアンス項目表 |
| 7. 教育・定期レビュー | 継続改善サイクル | e-Learning教材/半年ごとの棚卸計画 |
社内規定作成時に必ず確認したい4つの法規・契約
| 分類 | 要点 | 実務上のチェック |
|---|---|---|
| 個人情報保護法(改正動向含む) | 要配慮個人情報の入力禁止、取得目的外利用の回避 | マスキング・匿名化ツールを実装 |
| 経産省 AI事業者ガイドライン | リスク評価・説明責任・ステークホルダーへの透明性 | RACI表で責任分担を明文化 |
| OpenAI 利用規約(2025.1改定) | API経由データは学習不使用、コンテンツポリシー違反例 | プロンプトフィルターを設定 |
| 知的財産・著作権 | 生成物の著作権帰属、商標・肖像権侵害リスク | 出力物レビュー/ファクトチェック |
参考になる公開ガイドライン・事例集
| 種類 | ドキュメント/企業 | 公開日 |
|---|---|---|
| 官公庁 | 経産省「AI事業者ガイドライン Ver1.1」 | 2025/3/28 経済産業省 |
| 官公庁 | 個人情報保護委員会「生成AIサービス利用に関する注意喚起」 | 2023/6/2 個人情報保護委員会 |
| 企業 | NTT DATA 全社導入事例 | 2024/5/29 NTT DATA |
ガイドラインひな形
1. 目的
本ガイドラインは、生成AI「ChatGPT」を安全かつ効果的に活用し、企業価値向上とリスク低減を両立することを目的とする。
2. 適用範囲
全従業員・業務委託・派遣社員を含む。個人利用端末で業務データを扱う場合も対象。
3. 入力禁止データ
- 個人情報保護法で定義する要配慮個人情報
- 未公開の経営数値・顧客情報・秘密保持契約(NDA)対象資料
- 法務・IR・監査等の機密資料全文
4. 推奨ユースケース
- 議事録要約・翻訳・コードレビュー・FAQ草案作成
- 非定型文書のたたき台作成(公開前に必ずレビュー)
5. セキュリティと監査
- SSO認証必須、VPN外からのアクセス禁止
- すべてのリクエスト/レスポンスを30日間保存し、AIガバナンス委員会が監査
6. 教育・サポート
- 半期ごとにe-Learningを必修
- プロンプトテンプレートライブラリを社内Wikiで共有
よくある質問
| Q | A |
|---|---|
| 社員が個人アカウントで使う場合も規定が必要? | はい。業務データを扱う恐れがあるため、個人利用も範囲に含めるべきです。 |
| API経由なら学習に使われない? | OpenAIはTeamプランやエンタープライズプランはデフォルトで学習不使用ですが、契約や設定ミスに備え確認を推奨します。 |
まとめ
- 社内規定は「データ保護・品質担保・法規遵守・教育」の4軸で設計する
- 経産省ガイドラインやPPCの注意喚起を基準に、会社固有の業務プロセス・データ分類を上乗せする
- 導入後もログ分析と定期レビューを行い、生成AIの進化や法改正に合わせて継続改善することが成功の鍵です
AIについての無料相談のご案内
株式会社MoMoは様々な企業様へAIの導入支援を行なっております。
貴社のビジネスを次のステージへと導くために、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。専門のアドバイザーが、貴社のニーズに合わせた最適なAIの導入方法をご提案いたします。この度の記事ではご紹介できなかったその他の生成AI活用方法を知りたい方は、無料相談にて詳しくご説明させていただきます。皆様の無料相談のご予約をお待ちしております!